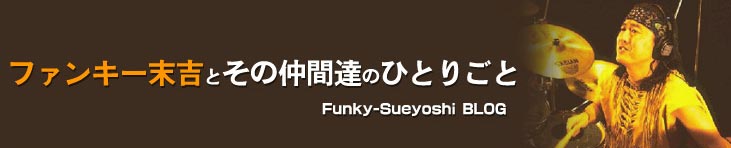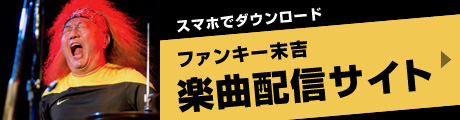2022/01/15
レコーディングで一番大切なこと
先日、いつものような「速度戦」で1日半で全ての伴奏を完パケした。
久しぶりの生バンド録音で感じたこと、再確認した「レコーディングで一番大切なこと」を記しておきたいと思う・・・
まず、レコーディングに限らずドラムで一番大切なことは、「リズムが一定」であること、そして「音量、音質が一定であること」、
これが最近では(昔からか?笑)波形データを見てみれば一目瞭然!!
一番下の2段がバスドラ、その上2段がスネアである。
そして縦の線が機械が設定する絶対正しい1拍1拍の位置・・・
見てもらえばわかるようにぴったりとその線に合致している!!(ドヤ顔)
まあこんなこと考えてなくても、(クリックとか打ち込みに合わせて叩く場合は)「いいプレイをした〜」という時は自然とこのような状態になっているものである。
そして音量!!・・・波形の大きさを見てもらうと、スネアを見ると一目瞭然だが、全く同じなものが続く・・・
これはすなわち、同じ部分の中でリムとかの当て方を変えない限り「音質」も同じである!!
(音質の使い分けに関してはこちらを〜)
バスドラはばらつきがあるように見えるが、よく見ると小説の頭(縦の線の上)は毎回同じである。
また、これは「ばらついている」のではなく「そう叩いている」のである。
バスドラをふたつ連続で踏む時に、ひとつ目は軽く、ふたつ目は強く叩いていて、その大きさの比率は毎回同じである。
これがこのブログで書いてるように、ひとつのパートではこれらを勝手に変えてはならない、それが「安心感」として伝わり、「安定感」となる。
ここにばらつきがあると聞いてる方が入り込めないからね・・・
ところが矛盾するようだが、逆もまた真なり!!
このピアノの録音を聞いて欲しい・・・
これがねぇ〜よくってねぇ(涙)・・・自分でピアノを打ち込んでベロシティーとかいくら調整してもこうはいかん(>_<)
先程のドラムの話と違って全く同じ音量音質だと「機械」になってしまうが、これは「ばらついている」のではなく、「歌っている」のである!!
これがブログで書いた「ドラムで歌うということ」である。
今にして思えばピアノを例に出せばうまく説明できたのだが、「音を小さく叩く」ということと、このように「歌う」ということは全く違う。
この、イントロでフォルテッシモで弾いているピアノが、Aメロになった時に突然弱く弾いている、その「弾き方」に涙するのであって、ただ「弱く弾く」でこのような効果は現れない(当然やな)・・・
このブログで書いたのは「全体の中のパートパートでの歌い方の違い」であるが、厳密に言うと1小節内にもそれはある。
Jazzみたいにボトムを支える何かの上で漂って叩くドラムの場合はまた違うのだが、ロックやこの流行歌のようにドラムがボトムを支える場合にはやはり1小節目と2小節目、そのパートの全部は安定していないとキモチワルい。
でもハイハットや、スネアのゴーストノート、そして先程のバスドラの大きさの違いとか、1小節単位では細かい違いがある。
これらは決して「ばらついている」のではなく「起伏」なのである。
またドラムはその1小節や、まあ2小節パターンの場合には2小説の「うねり」と、曲を大きく見た時の1コーラス全体の起伏や、サビなどの盛り上がりに向かうその直前の数小節の起伏や、色んなものが総合して「表現力」となるのである。
さてここまでは「安定感」の話・・・レコーディングで大切なことを綴ってゆきたいと思う・・・
ちなみに現代のレコーディングは「パンチイン」を前提としたレコーディングである。
間違えたらその場所から、もしくは後からその場所だけを録り直したり出来る。
ところが昔は違った。
はるか昔のアナログレコーディングの時代、アナログのマルチテープレコーダーというのは「消去ヘッド」と「録音ヘッド」というものが並んでいて、「消去ヘッド」で前に録音したものを消しながらそのちょっと後にある「録音ヘッド」で新しい音を録音してゆく・・・
つまりこの距離にタイムラグがあるので今の時代みたいに簡単にパンチインパンチアウトは出来なかったのである・・・
特にドラム!!・・・爆風スランプがファーストアルバムを録音していた時代には、
「最初から最後まで間違えずに叩く」
ことがレコーディングの前提であった!!
実の話、爆風スランプのデビューアルバムのレコーディングの時に、何かの曲でいつも最後まで叩けなくて、ソニースタジオのトイレで泣いた(涙)
「自分はこんなに下手だったのか(涙)」・・・これが今の私に至る「出発点」である。
今でもそれはある・・・レコーディングはいつもそれを教えてくれる「先生」である・・・
いつから時代が変わったのかはわからないが、ある日「かまやつひろし」さんのトリビュートアルバムをプロデュースさせてもらった時、ブッキングした二井原はんと、ゼノン石川くんだっけなぁ・・・みんながスタジオで待っている間、いつものように最初から最後まで間違わないようにドラムをレコーディングしてた・・・
ところが歌まで終わって飲みに行った時に二井原が私にこう言ったのだ。
「ファンキーもプロやからな、言わんかったけど、何で間違えたらそこから録り直さへんの?樋口っつぁんなんかいつもそうしてるでぇ〜」
これには心底びっくりした!・・・知らないうちに時代が変わっていたのだ!(◎_◎;)
ところがこの昔の時代の長い経験が、自分にとっては今では大きな財産になっている。
難しいオカズとか、叩けないフレーズは絶対に入れない!!
絶対に間違わない確実なものしか入れてゆかない!!
だからこうしてデジタルの時代になっても、新しい世代と比べたらやはり「安定感」が全然違う・・・
今となっては叩きながら「あ、ここイマイチやなぁ〜あとでパンチインしよ」とか思いながら叩いたりするが、それでもそのパンチインしようと思っている部分は、別に絶対に差し替えなくてはならない大きなミスではない。
「歌い方」とか細かいニュアンスがもっと出せたのでは?・・・という「欲」である。
それがあるからこそ、今回のようにドラムを叩き終わった後にアレンジャー、プロデューサー(今回はレコーディングエンジニアも兼任(>_<))として他の人を上に導くディレクションが出来るのである。
前述のピアノの録音、Aメロがとてもよくて泣きそうになってて、その後のBメロから録音し直す時に、「繋がらない」という問題が発生!!・・・つまり、前のニュアンスと後から弾くニュアンスが全く違うのだ・・・(レコーディングあるある)
そんな時には前のテイクを聞いてもらって、「このニュアンスで次も弾いて」とお願いする。
このピアニストはそれが出来た。でもベーシストはそれが出来ない(>_<)
「前のテイクはここ8分音符で休符を入れて次に行ってるけど新しいテイクはレガートで弾いてるよね!!」
そう言ってもわからない(>_<)・・・自分がどう弾いていたかもわからないのである(涙)
こういう人は、もしわかったとしても同じように弾けない(>_<)
それは「まぐれ」でいい演奏が出来ただけであって、同じように再現することは出来ないのだ。
つまりレコーディングで一番大切なことは、「自分の歌い方を全部理解している」ことなのである。
ついでに言うと、プロ中のプロはそれを全部「覚えて」いる!(◎_◎;)
2000年代中盤、北京のスタジオミュージシャンとして一番売れていた頃は、この国のトップミュージシャン「李延亮」というギタリストとよく一緒に仕事をした。
ある時は彼のプロデュースする作品にドラマーとして呼ばれ、ある時は私のプロデュースする作品にギタリストとして呼んだ。
その時の話、ギターのバッキングが2番でちょっとニュアンスが違ったので、
「これ、1番とはちょっと違うよね、同じに弾いてくれる?」
とお願いした。
通常ここで「OK〜じゃあ一回聞かせてくれる?」と来るが、彼の場合、自分がどう弾いたかは全部覚えているので聞く必要がないのだ!(◎_◎;)
更に恐るべきことに、ギターソロの一部分をパンチインしようとした時に、
「いいよ、じゃあ最初から全く同じに弾くから」・・・!(◎_◎;)
つまり彼には全く「まぐれでこれが弾けた」というものがないのだ・・・(凄っ)
ちなみに彼は速弾きとかの超絶テクニックのギタリストではない!!
指が速く動くということならこの広い中国、彼よりも速いギタリストはいくらでも見つかるだろう、
でもレコーディングの数、稼いだ金、名声、彼を超えるギタリストは誰もいない。
中国の若いドラマーが私のところにドラムを教えて欲しいと来る・・・
私がいつも言うことはこんなことである。
金を稼げるドラマーになりたかったら、超絶テクニックとかを勉強するより、「リズムが正確」「音量が一定」「音色が一定」、これに尽きる!!
そして更に進んで、楽曲の把握能力。
どこで盛り上げてどこで落とすか、その構成力(つまり「歌い方」)
そしてレコーディングでは(ライブでもそうだが)まぐれ当たりを狙わない!!
確実に出来ることの中で、自分が思う最大の曲をよくする叩き方をプロデューサーに提供する。
スタジオミュージシャンの場合、万が一プロデューサーが気に入らなかったら代替え案を出せる柔軟性も必要。
「まぐれ当たり」ではなく「確信犯」としてやっているわけだから、「もう一度」とか言われたら当然それが出来る。
現代のレコーディングにおけるパンチインパンチアウトは必ず「繋がる」わけだ。
まあこれが出来れば別にパンチインしなくても最後まで叩けるだろう・・・
パンチインはあくまでそこから上に行くための次の手段と考えておこう〜
要は「確信犯」として演奏しなさいよ、それがレコーディングでは一番大切だよ、ということである。