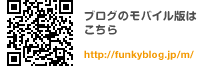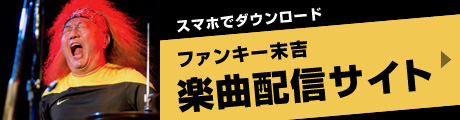
2021年11月10日
オープンハンドはバラードにも有利
さて、夏に1ヶ月半籠って練習した甲斐があって、今ではコンサートで左右の腕を交差させて叩くことは全くない!!
最初の取っ掛かりでも書いたように、元々はこの曲の叩き方から始まった・・・
今では右手が「2、4」をちゃんと打って守りを固め、左手がリーダーシップを取って細かい装飾音符でリズムを彩ってゆく・・・
当初の目論み通り、左右の腕が交差しないので右手が解放されて自由度が上がり、1分3秒とか1分46秒辺りの小さなフィルなどは、両手が交差している状態では絶対に叩けないフレーズである。
また、この曲の構成はA-B形式なので、Aはハイハット、Bはライドを叩くようにしているが、2番が終わったらセクションを挟んで二胡のソロ、まあこれもライドでいいのだが、次のギターソロも同じくライドではちょっと変化に乏しい・・・
かと言ってハイハットに戻るとタイトになって盛り上がりに欠けるのでツーバスを踏みながら左手で左側のライド(今回はそれ替わりのクラッシュ)を叩く。
Jazzの人がメリハリをつけるために左側のシンバルでレガートを始めるようなもんですな・・・
これも別に右手でライドを叩けば手順は同じなのだが、腕が交差するのを嫌って手順が全く逆になるけど左手で!!
いや〜練習の時にはまさかこんなことが出来るとは思わんかったけど、本番のアドレナリンって凄いな!!・・・左手が勝手に3つ連続打ちとかしよる(笑)
本番のアドレナリンがさせているのはそこだけではない。
サビや二胡のソロの部分、いわゆるシャッフルのレガートは2泊3連で打つのだが、ギターの3拍4つ取りに合わせてこんな複雑なリズムが叩けるようになった!(◎_◎;)
まあきっとこれを左手でやってももう叩けるじゃろう・・・練習の時はいくらやっても出来んかったのに〜(>_<)
そしてここから本題!!
アンコールにいつもやるロックバラード!!
まあ作った人はこれをロックバラードと解釈しているかどうかわからんが、ドラマーが「ポップス」ではなく「ロック」と解釈して叩いている・・・
何が違うのかを今から説明しよう・・・
まず私は大きく分けて4つのスネアの叩き方を使い分ける。
音量の大きな順に、
1、リムに当てたスネアショットを強く叩く音
2、リムに当てたスネアショットを弱く叩く音
3、リムに当てずにスネアを強く叩く音
4、リムに当てずにスネアを弱く叩く音
例えばイントロは1で叩いてAメロで4に落とし、Bメロで2、そしてサビはまた1・・・
とか、これにハイハットやライドやカップなど、スネア以外の叩く部分を変えることによってそれぞれのパートがくっきりと区別されて「構成」がくっきりと浮き彫りにされるというわけだ。
私はスタジオミュージシャンとしてここ中国でもう数百曲のレコーディングをしたが、中国ではそのほとんどがバラードか、速くてもミディアムテンポの曲である。
中国の多くのドラマーは
「Funkyさんの超絶テクニックの曲は難しくて叩けないけど、バラードぐらいだったら誰でも叩ける」
と思っているが、逆である!!
「スローボールは力のないボールではない!!思いっきり遅い球を投げるんだ」
という話をどっかで聞いたことがあるが、同様に
「小さい音は弱く叩くのではない!!思いっきり小さな音を出すのである」
それが表現力!!
・・・そしてそれを楽曲の構成と共に自分の解釈で散りばめる・・・
それが「歌う」ということなのである!!
ところが通常の左右の腕を交差させる叩き方では、右手がハイハットを叩いていると左手は上まで振り上げられないので、現実的に「3、リムに当てずにスネアを強く叩く」というのは無理である。
右手がライドとかを叩いている場合には更に多彩に、1とか3とか、「強く叩く」と言っても大きく分けて2通り、力を抜いて大きく振り下ろして落とす感じで叩く音と、低いところから力を入れて強く叩く音、そして大きく振り下ろして更に力を入れて叩く音とはその音量、音色共に大きく変わる。
これも右手でハイハットを叩いていると、左手は大きく振り上げられないので選択肢が大きく狭まることになる・・・
力を入れるか抜くかで何が変わるかと言うと、特に音色である!!
通常、リムと共にスネアを叩く音色は、力を抜いて大きく振り下ろした音色が一番抜けが良い。
力を入れるとちょっと篭ったような音色・・・そして大きく振り下ろして力を入れる最大音量の音色はスネアが悲鳴を上げているような・・・
そう、それが「ロック」の音色なのだ・・・
この映像を見ていただこう・・・
構成ごとに追ってゆくと、まずイントロ(0:33から)はライドを叩いて、スネアはリムに当てて力は抜いているが、自分の頭の後まで大きく振り下ろしながら叩いている。
この音色が一番抜けもよく、感情も一番平穏ないわゆるこれがこの曲の「基本」である。
Aメロ(0:49から)はリムに当てずに軽く叩く・・・しかし右手でハイハットを叩いていると、腕が交差して大きく振り上げられないので必然的にもっとボリュームが下がってしまうが、オープンハンドではこのようにイントロと同じように振り上げて、しかも力を抜いてリムを外してスネアを叩くことが出来る。
ボリューム的にはそんなに変わらないが、音色が全く違うのがお分かり頂けるだろう。
ちなみに1:18のフィルは、オープンハンドでないとハイハットを叩くのをやめないと叩けない・・・
フィルの後には同じAメロで同じぐらい振り上げていてもちょっと力を加えている。
そうするとまたちょっとだけ音色とニュアンスが変わって来るのだ。
リイントロ(1:51)ではそれを受けてちょっとイントロよりは力を入れる。
それが流れとしては自然である・・・
まあ力を入れると言っても振り下ろす時に重力と共に腕の力を加えているという程度であるが、次の2番のAメロ(2:23)では明らかに「力を入れて」叩いている。
何故ならボーカルは1番と違って高い声を張り上げているわけだから、ここで1番のように抑えて叩くのはニュアンスが違う。
かと言ってイントロのように盛り上げるところでもない。
だから「精一杯の力でスローボールを投げる」のである!!
サビ(2:53)からはリムも叩くし力も入れる。
スネアが悲鳴を上げているように聞こえはしないか?(笑)
これが「ロック」の音色である。
私自身がこの曲を「ポップス」と解釈した場合、ここでこの音色は使わない。
イントロと同じか、もうちょっと力を入れたぐらいの音色にしておく。
そのドラマーのニュアンスの違いで曲のイメージは大きく変わるのだ。
このパートの最後のフィル(3:22)では一番強く叩く音色、私はこれを「根性ボタン」と呼んでいるが、これが電子ドラムでは出し得ない生ドラムならではの表現、ベロシティーが127と目一杯な上に更に渾身の力を入れて叩くと「プラス根性」となり、ドラムセット全体が悲鳴を上げているような音色になる。
(実際悲鳴を上げているのだろう笑)
これが「ロック」の音色なのである。
その後のギターソロは決して静かに下げる部分ではないし、かと言ってサビより広がる感じではない。
だからハイハットをオープンで叩いているのだが、ここでハイハットを右手で叩くとスネアを叩く左手をここまで振り上げられないので音色が変わる、すなわち「盛り下がる」。
オープンハンドならではでスネアだけは全く音色が変わらずにライドからハイハットに移行出来るというわけだ。
そして3:54からの盛り上がりはこれ以上ないというぐらい力を入れて大きく振り下ろす音色。
イントロと比べると同じ「1、リムに当てたスネアショットを強く叩く音」でも全く音色が違うのがわかって頂けるだろう。
そして4:25からのエンディングは、更に盛り上げるべく左手でクラッシュ(左側にライドがあるとライドを叩く)を叩いている。
これも「構成力」のひとつですな。
ちなみにこれは即興でやっているのではない。
レコーディングの場合は一回通して叩いた時に全体像を見てこれらの割り振りを考える。
この曲にはゴーストノートがないからまだいいが、ミディアムテンポの曲の場合は更にゴーストノートの音の大きさ、散りばめ方でまたニュアンスが大きく変わって来る。
大事なことは、同じ構成の部分は1小節目がどうだったとすると、その後も全く同じに叩かなければならない。
速くなったり遅くなったりはもちろんのこと、同じ構成の中で強くなったり弱くなったりもご法度である。
どうだろう、これこそが「バラードの叩き方」、そして「ドラムでの歌い方」である。
オープンハンドになったことで更にその表現の幅が広がったということだ。
ドラマーの皆さん、別に無理してオープンハンドにする必要はないが、「ロック」をやるなら「音量」!!小さな音でしか叩けないドラマーはそれだけ「表現力がない」ということである。
私のような身体の小さなドラマーが音の大きさでは人に負ける気がしない。
それはこの映像のように「振り上げる高さ」なのである。
ボリュームを司るのは「力」ではない「スティックの先端の速度」、そして「力を入れる」ことによって「音色」が変わる。
ドラマーの諸君!!
「表現力」を手に入れて、それを自分なりに表現してみよう!!
それが「音楽」なのだ!!