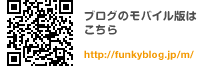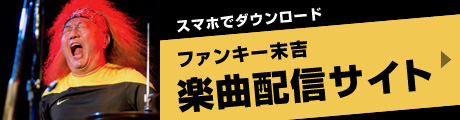
2018年12月31日
SING THE BLUES FOR YOUライナーノーツ
01:最後までよろしく
(作詞:ザビエル大村・三井雅弘 / 作曲:ザビエル大村)
私が大村はんと出会ったのは2000年春のこと。
X.Y.Z.→A (エックス・ワイ・ズィー・トゥ・エー:Vo 二井原実、 G 橘高文彦、B 和佐田達彦、Ds ファンキー末吉)というバンドで「100本ツアー」と銘打って日本全国をくまなくツアーで廻っていた。
二井原実が喉の不調により関西方面のライブが何本かキャンセルになってしまい、共通の友人"三井はん"の紹介で大村はんのマンションに初めて泊まりに来た。
マンションには「ギター部屋」があり、見たこともないようなギターがいっぱい並んでいた。
その中から一本を取り出して弾いてくれたのがこの曲。
ギター1本でベースラインから伴奏、メロディーまで奏でる「ラグタイムギター」という奏法に度肝を抜かれた。
02:淀川リバーサイドBlues
(作詞作曲:ファンキー末吉)
谷町線「守口」駅からほど近い、淀川を見下ろせる
大村はんのマンションにあるCDはそのほとんどがブルース。
大村はんがギターを爪弾いてもその全てはブルース。
朝起きてからそんなブルースばかり聞いていたら、ついつい酒を飲みたくなる。
昼間っからウィスキーの水割りを飲みながら「ええなぁ」とブルースに酔いしれる。
当時このマンションの近所に「へんこつや」というホルモン屋があり、夕方にはそこに行ってホルモンを食う。
そんな数日間の生活でだんだんわかって来たのだが、このマンションにはちょっと前まで「嫁」がいたらしいが出て行ってしまったらしい。
「歌になるなぁ...」ということで出来上がったのがこの曲。
03:ハゲでよう見たら背もちっちゃいからずんぐりむっくりやけどそれでも今日からあたいの大事なだんな様(仮)
(作詞作曲:ファンキー末吉)
「髪」、いや「神」というのはいるもんなんですなぁ・・・
そんな大村はんにも「二人目の嫁」がやって来た。
爆風スランプの追っかけの双子姉妹のひとり。
双子というのは面白いことに二人でいつも一緒にいる。
学校も同じ、卒業して職場も同じ、趣味も同じ爆風スランプ、妹はサンプラザ中野、姉はファンキー末吉のファン。
また面白いことに双子というのは二人を一緒くたにされるのが嫌らしい。
「だったら一緒におるな!!」という話なのであるが、姉は姉、妹は妹、ちゃんと一人して区別してくれる相手じゃないと、結婚どころか恋愛とかも絶対にダメらしい。
そこで「髪」ならぬ「神」が登場!!
ある日、同じ大阪でサンプラザ中野のライブとファンキー末吉のライブが同じ日に行われたのである。
双子の姉妹はここで初めて別々に別れてライブを見に行くことになり、私のライブにひとりで来た姉を大村はんに紹介し、トントン拍子に結婚と相成った。
私は新郎新婦の紹介者として結婚式の仲人となり、披露宴で歌うこの曲を作ってプレゼントした。
思えばこの結婚式以来誰も歌うことがなかったこの曲を、私自身が歌い継ごうと思い今回アルバムに収録した。
タイトルは今だに仮タイトルのままである。
04:おお BEIJING
(作詞:サンプラザ中野、作曲:ファンキー末吉)
爆風スランプが「Runner」「リゾ・ラバ」などヒット曲を連発していた頃、実は私の精神状態は一番よくない状態であった。
毎日テレビの娯楽番組などで忙殺され、「芸能界」というところが大嫌いになり、「自分は何をやっているんだろう」という思いがピークになって来たある日、友人の鍼治療に同行して初めて中国に旅行に行った。
その時偶然地下活動をしている中国のロックバンドのライブを見た。
血が逆流するほどの感動の中で「俺は中国人になる!!」と言って今に至る。
若かりし頃、黒人音楽を初めて聞いて「俺は黒人になる!」と言ってアフロヘアーにし「ファンキー末吉」と名乗って以来の人生の大転換である。
頃は1990年、前の年に起こった天安門事件以来、一番締め付けが厳しい時代の中国で、地下活動としてロックをやっている若者たちのことを思ってこの曲を作った。
サンプラザ中野はこの曲に天安門事件の民主化のリーダーの一人とその恋人をモチーフにしてこの詞を書いた。
05:ママの初恋
(作詞作曲:ファンキー末吉)
北京から帰った私は「心ここに在らず」でいつも中国ロックのことばかり考えていた。
爆風スランプが活動停止となったのもこれがひとつの大きな原因である。
そんな中、私は中国ロックを題材に小説を書き、それが「小説現代」に掲載され文壇デビューすることとなる。
この「天安門にロックが響く」という小説は、その後「北京の夏」という漫画の原作となり、それが翻訳されて香港、台湾で発売された。
中国共産党が支配する中国大陸ではもちろんご法度である。
私の嫁(当時)は中国人で、その両親が初めて日本に来てこの漫画を見つけた時、私にそれはそれはこんこんと説教をした。
「中国では絶対にやってはいけないことが二つある。
ひとつはエッチ系、そしてもうひとつは政府批判」
そしてこう強く念を押した。
「家族のうち誰かがそんなことをしていただけで、ひょっとしたら一族郎党殺されていまうかもわからないのよ」
そんな時代である。
だが私は当時、天安門事件で恋人を殺されるこの小説の主人公である女性ロッカーをモデルにしたこんな曲まで作っていた。
これは当時作ったコンセプトアルバム「ある愛の唄」の主人公(この女性ロッカーの子供)が、子守唄として母親から恋人との恋物語を聞くというお話である。
(小説はこちら、コンセプトアルバムの詳細はこちら、別バージョンのこの曲のMTVはこちらにあります)
06:あんた好みの女
(作詞作曲:ファンキー末吉)
その時代、私はよくオカマバーに飲みに行ってた。
年老いた化け物のようなオカマが経営する小さなスナックに行くと、「ようこそお化け屋敷に〜」とそのママさんがドスの効いた声で言うのが好きだった。
そこのメグちゃんという筋肉隆々のオカマ。
彼氏に振られたらしく私が一生懸命慰めていた。
「それでね、彼ったらね、腹いせに女なんか連れて来たのよ〜」
さめざめと泣きながら涙を流すメグちゃん。
「それで?どうなったの?」
「もちろん半殺しにしてやったわよ」
心は女、でも身体は筋肉隆々のメグちゃんが好きだった。
後に化け物のようなママさんが私にこう言った。
「あんたあの娘のこと好きでしょ、ダメよ〜あんたは女ともすぐに友達になっちゃうでしょ、そんな男はオカマにはモテないの。オカマはね、ち○ち○好きで人間捨てたのよ〜オカマ好きになるならすぐにやっちゃわないと」
オカマの世界も深い・・・
私もいつかこんなオカマと手を繋いで街を歩いてみたいものである、という曲。
07:あたいの100$の恋
(作詞作曲:ファンキー末吉)
売春婦に本気で恋をした男がいた。
貧乏なミュージシャンなのであるが、金が入ると彼女に全部使っていた。
無口な男なのだが、ツアー中に電話がかかって珍しく長話をしているのでついつい聞いてしまった。
「だからツアーなんだよ。仕事なんだ。帰ったらすぐに会いに行くから」。
女性と縁遠かった彼がやっと恋人が出来たのかと思ったらその売春婦だった。
「え?でも普通に一緒に食事したりしてるんだったらもう恋人じゃん」
私なんかは単純にそう思ったのだが、
「だって、やったらお金払わなくちゃなんないし・・・」。
私は彼にこう聞いた。
「でも・・・君は彼女のこと好きなんでしょ?」
これはちょっと困った顔でこう言った。
「いや、そんなにお金ないですから」
返答に困っているのか質問と答えが微妙に食い違っている。
「じゃあお金あったら結婚したいとか思う?」
「いや、お金ないっすから・・・」
また質問と答えが微妙に食い違う。
「もしあったらの話だよ。結婚したいと思う?って聞いてるの」
彼はちょっと間を置いて小さく頷いた。
涙なしでは歌えないBluesである・・・
08:Merry Christmas Blues
(作詞作曲:ファンキー末吉)
2000年ぐらいに北京に居を移した私に飛び込んで来た色んな世界情勢のニュースの数々。
アメリカの同時多発テロ、その対テロ戦争としてのアフガン侵攻・・・
そんな北京である日、ギターを爪弾いてたらふと浮かんだこのメロディーと歌詞。
遅筆な私には珍しく、最後まですらすらと歌詞が出来上がった。
そこでは生きていてもどうしようもないというほど悲しみに満ちた女性が世界平和を祈る。
その後とある中国の有名歌手がこの曲を歌ってくれて、その歌手が愛してやまないこの曲を作ったのが私だと聞いて涙を流して抱きついて来た。
(その時の話はこちら)
この歌手にこんなにも愛されて、この曲はなんて幸せなんだろう、そして作った私もなんて幸せなんだろうと思った。
この曲はそうやって世界平和を願う多くのシンガーに歌い継いでもらいたいと、心からそう思う。
09:Star
(詞:渡辺英樹、作曲:丸山正剛)
一世を風靡したバンド「C.C.B.」のベーシストでありリーダーでボーカリストの渡辺英樹さん、
彼の最後のバンドとなった「VoThM」のレコーディングが北京で行われ、それが最後のアルバムとなって彼は帰らぬ人となった。
この曲は、その時にレコーディングされた曲である。
基本的に自分の作った曲しか歌えない私が、それからこの曲を歌い継ごうと決意した。
毎回毎回ライブの時に、
「あんたほど上手くは歌えないけどね」
と天国の英樹さんに言い訳しながら歌う。
「かっかっかっ」・・・生きてる頃の高笑いが聞こえてきそうである。
ところが北京の自宅でひとりで真夜中にこのテイクを録音している時に、いつもは絶対出ないようなこんな声や歌い方が突然出来た。
どうしてなのかわからない。
こんなテイクはもう二度と録れないだろう。
「かっかっかっ・・・その後のライブでは頑張ってこんな風に歌いなはれや!!」
天国で英樹さんがそう言って笑っているような気がした。
10:What a Wonderfull Night
(作詞作曲:ファンキー末吉)
私は、はすっぱな女が好きである。
まだ会ったことはないが自分のことを「あたい」と言い、相手のことを「あんた」と呼ぶ・・・
そんな女が本当に絶望したらどんな気持ちなのか・・・
そんなことを考えながら多くのBluesの曲を作ってきた。
しかしこの曲の主人公は珍しく男性である。
同様に人生に絶望し、この相手こそはと思った相手が、朝になったらいなくなってしまうことを知っている。
それでも「なんて素敵な夜なんだ」と歌う・・・
男性版Bluesの決定版である。
11:キーキー言われてもーたBlues
(作詞作曲:ファンキー末吉)
「世の女性という生き物は、どうしてあんなにキーキー言うのだろう」
世の男性は、口には出さないもののみんなこのように思っているに違いない。
ある時にアマチュアミュージシャンのジャムセッションでとあるベーシストに会った。
彼は本当に楽しそうにベースを弾き、そして本当に美味しそうに酒を飲む。
そしてこんなことを言うのだ。
「幸せだなぁ...ほんっと、金がないのと嫁がキツいのを除けば人生はほんっと楽しい!!」
この話を題材に、詞だけ書いてツアーに持って行った。
曲なんかは
「キーはDの3コードのブルース。手ぇ挙げたらブレイク!」
これだけでBluesの曲なんかすぐに出来てしまうのだ。
ライブの度に歌い回しやメロディーなどを変えてゆき、キーがDからEに、そして最後には金切り声のGまで上がり、ギターもオープンチューニングのスライドギターになって完成されたライブバージョン。
こうして全世界の男性の心の叫びを代弁するBluesが 出来上がった。
12:人は何で酒を飲むのでしょう
(作詞作曲:ファンキー末吉)
2000年に私がプロデュースしてデビューした「三井はんと大村はん」の代表曲。
当時のレコード会社にはJazzのレーベルがあり、そこで私のJazz系のユニットがレコードを出させて頂いていたためにそのレコード会社から発売させて頂くことになった。
ところがそのJazzのプロデューサーのトップの方が私の事務所に打ち合わせに来た時に、出来上がったばかりのこの曲が事務所で流れていた。
そのプロデューサーは打ち合わせを中断してこの曲に聞き入り、そしてこう言った。
「末吉くん、この曲は・・・哲学だよ!!」
ライブバージョンなので途中の間奏に喋りが入っている。
「結婚は判断力の欠如!離婚は忍耐力の欠如!!そして再婚は記憶力の欠如!!!」
哲学である・・・
13:65歳の地図
(作詞作曲:ファンキー末吉)
1989年にリリースされた爆風スランプの楽曲に「45歳の地図」という曲がある。
奇しくもちょうど20年後にこの「65歳の地図」という楽曲がリリースされることになるのだが、残念ながらアンサーソングではない。
「45歳の地図」は主人公が息子に、中学校の文集で「親父のようにはなりたくない」と発表されるお話だが、こちらの設定は息子ではなく娘。
定年退職を目前に控えて熟年離婚されるサラリーマンの悲哀と娘への愛情を歌った曲である。
私の友人にモリタカシという人間は存在するのだが、そこの家庭の物語ではない。
別の友人「E」の家庭が、実際に自分の部屋に食事を運んでもらってひとりで食べてたところからこのストーリーを思いついた。
もっとも「E」は同じ家にいながらご飯のお代わりが欲しい時は嫁にメールしていたのだが・・・
この曲のMTVはこちら〜
これら楽曲はこちらからダウンロード購入出来ます。
(視聴も出来ます)
Posted by ファンキー末吉 at:11:54 | 固定リンク
2018年12月27日
裏おすし
Jazzなのだから毎回演奏は違う。
「失敗」も含めて、「人生」と同じでそれも含めてひとつの「作品」である。
今回「おすし」の「いただきます」をライブ録音するに当たって、ワンツアー全てのライブを録音して、結果一番勢いのある最終日2日間の録音を採用した。
しかし他のライブにもいいテイクがいっぱいあった・・・
というわけで、「いただきます」と全く同じ曲順で、テイク違いのアルバムを作ろうと思い立った。
タイトルは「ごちそうさま」(笑)
「いただきます」はこちらでも販売しているが、「ごちそうさま」はライブ会場のみでCD-Rにて販売する。
配信はこちらにて両方ゲット出来るので、コアな人は両方揃えて聞き比べてみるとよいと思う。
配信では詳しいディティールを書ける場所がないので、下記にそれぞれのディティールを解説と共に書いてみたいと思う。
まず、ミックスは予算がないので私自身がやらせて頂いた。
そのせいかドラムがちょっと大きいなというテイクもあるかも知れない(笑)
あと世俗的過ぎると言うか、小市民と言うか、
「いただきます」は拍手はなるだけ切っているのに対して、
こちらの方は思いっ切り大きく、そして長く入れてあるのであわや74分のCDに入らなくなるところだった(笑)
マスタリングはファンキーStudio北京の方言(FangYan)。
銭金抜きでやってくれたのはいいのだが、その分こだわり過ぎて・・・(>_<)
まず最初のバージョンが送られて来た時にはびっくりするぐらいよくて小躍りしたもんである。
ところがしばらくして「あのバージョンはダメだ」と言い出して、またしばらくして2つ目のバージョンが送られて来た。
これが私としては個人的には気に入らない。
いじり過ぎてて何か人工的過ぎてJazzっぽくないのである。
やり直しをお願いしたらそれから1ヶ月音沙汰なし!(◎_◎;)、
この前北京に帰った時に聞いてたら、更に5つか6つバージョンを作ってたらしい。
「もうええから提出しなはれ」
と言って提出させたバージョンがこれ。
工場に納めた後も
「Funky老師〜またちょっと直したいんだけど・・・」
と言うので
「もうええわい!!工場に入れたわい!!」
と言ってやり直しを拒否した(笑)
まあ録音した場所が違うので一概には言えないが、「いただきます」に比べて音が太い印象がある。
「いただきます」が「白」のイメージだとしたら、このアルバムは「木目」のイメージ。
シンバルレガートの音がシンバルというよりスティックの木の音が強く聞こえているような気がする。
それではそれぞれの曲の解説を・・・
(「いただきます」「ごちそうさま」共通の解説も含む)
01:The Door To 7th Heaven(2018年10月22日高田馬場音楽室DXのリハーサル)
これだけが「いただきます」と同じ高田馬場音楽室DXでの、こちらは本番ではなくリハーサルのバージョン。
この曲はライブ毎に色んな変更点を加えていって、結局この最終日にやっと完成形となったのでこのテイクしかなかったのだ。
ちょっと聞くと「いただきます」と「ごちそうさま」どちらがどちらのバージョンかわからない演奏である。
最初の小さなドラムソロの部分は、「いただきます」と同じフレーズを叩いている。
これは8分の7拍子のソロの部分にいきなり4分の7拍子になるフレーズを叩くので、リハとして
「本番ではこんな風に叩きますからね」
と叩いたものが採用されてしまったからである。
まあJazzとしては少し残念だが、これも含めて「テーマ」と考えれば納得がゆく。
(この曲のエピソードはこちらにもあります)
02:ろう君の初恋(2018年10月15日名古屋Breath)
これはもう長くやっているのでどのテイクも甲乙付け難い。
このバージョンはツアー初日のバージョン。
Breathのドラムは他の店と違ってロック系のドラムセットで、タムもフロア含めて4つ並んでいるのでタム回し系のフレーズが多い。
この店だけ定位が他と違ってドラムが真ん中、ベースが左で、ピアノが右となっている。
03:Dream Express(2018年10月18日京都RAG)
京都RAGはピアノが生ピアノなのが特筆すべき点である。
ピアノの定位も客席から見て後ろを向いているので右が高音部、左が低音部と「いただきます」の逆になっている。
ツアーのこのぐらいからこの曲のドラムソロの最後のフレーズがスティーブガッド系3拍フレーズに固定された。
ドラムソロのソロフォームは、テーマ部分を最初から演奏してサビの部分をXtimeで繰り返している。
サビに入ったところで1小節目と4小節目にテーマメロをもじったセクションが入るが、
次の小説頭で仕切り直さずそのまま叩くことによって小節感を不思議にしているところがミソである。
04:Dolphin Dance(2018年10月15日名古屋Breath)
ハービーハンコックの名曲で私の大好きな曲である。
最後のドラムソロでは、このライブで3連符の8つ取り、8ビートに聞こえるフレーズをやってみたら面白かったのでその後この曲ではずーっとそれをやっている。
05:Everything Is From the Sea(2018年10月18日京都RAG)
進藤陽悟のオリジナルで3拍子の曲。
3拍子は非常に自由なリズムで、2拍で取ってゆっくりの4ビートになったり、
3拍4連で取って早い4ビートになったりする。
生ドラムと電子ドラムと同じように、生ピアノと電気ピアノとは全く違う楽器である。
楽器が違うので当然「弾き方」が違う。
生ピアノバージョンならではのセッションをお楽しみあれ。
06:炎の靴(2018年10月18日京都RAG)
「いただきます」と比べて一番違うのが「テンポ」。
こちらのバージョンが落ち着いて聞こえるのは演奏が落ち着いているだけでなくテンポそのものが落ち着いているのである。
それにしてもあの重い生ピアノの鍵盤で電気ピアノと同じように軽やかに弾く進藤陽悟は大したもんである。
07:Diamond Dust(2018年10月18日京都RAG)
ジェフベックの「ブロウバイブロウ」に収録されている5拍子の美しい曲。
ピアノトリオでこの曲をやろうとなって3人で色々試行錯誤した。
まずテーマをベースが取った時に、分数コードの分母を弾く人がいなくなる。
そして今度はピアノがテーマを取った時に、分散和音のアルペジオを弾く人がいなくなる。
結局分数コードは何とかアッパーコードで解決し、
5拍子のアルペジオを左手で弾きながら右手でテーマを取るという風に落ち着いた。
ウッドベースは「作音楽器」と言って、ピアノのように「この鍵を押さえたらこの音が出る」というのではなく「音を探りながら演奏する」楽器である。
「歌えないメロディーは弾けない」らしく、この転調の激しいメロディーを一生懸命空で歌えるようにしていた大西さんが印象的である。
08:Memories(2018年10月15日名古屋Breath)
全中華圏で知らない人はいないというバンドBEYONDのボーカル黄家駒が日本のバラエティー番組の事故で亡くなったことを受けて、その香港での葬式の時に浮かんだメロディーで作った追悼曲である。
彼は今真っ白な気持ちのいい世界にいて、音楽家は「偶然」が重なって「名演」と呼ばれる演奏が出来た時だけトリップしたような感覚になってその世界に行くことが出来る・・・
09:Canal Street Samba(2018年10月18日京都RAG)
いつもアンコールで演っているサンバの曲。
途中のドラムソロは、いつの間にか出来るようになった「上下巻全分離」。
足ではずーっとそのままサンバのリズムを刻んでいるが、
手は3連の5つ取りや16符の5つ取り等を経て、最後には足はそのままで全く自由に叩くという、「ソロ」というよりは今やもう「芸」である。
10:ママの初恋(2018年10月18日京都RAG)
天安門事件で恋人を殺された女性ロッカーが、その娘に自分のその恋の話を子守唄として語るという曲のインスト版。
2018年年末が2019年初頭までに私は4枚のアルバムを出すが、その全てに収録されている曲である。
それぞれの配信はこちら
「おすし/いただきます」、「おすし/ごちそうさま」、「ファンキーはんと大村はん/SING THE BLUES FOR YOU」が現在(2018年12月29日現在)配信されてます。
コンセプトアルバム「ある愛の歌」ただ今制作中!!詳しくはこちら〜
Posted by ファンキー末吉 at:19:34 | 固定リンク
2018年12月26日
JASRACさん、こんな高飛車な仕事やってたら本当に告訴しますよ
念願の夢だった純Jazzのアルバムがリリースされた!!
(CDはこちらで予約開始、ダウンロード販売はこちらで今日から開始)
実はこれに関してJASRACと揉めたのが、1曲目に収録されている「The Door to 7th Heaven」という曲。
この曲はもともと中国で発売された私のソロアルバム「亜州鼓魂」の中に収録されている「天界への7番目の扉」という「組曲」の一部である。
私の尊敬するピアニストと、管弦楽のアレンジの師匠、つまり私の二人の偉大なる師匠との共作で作り上げた壮大な組曲・・・
ところが今回のJASRACとの裁判の中で、自分が演奏したこれらの曲に対してもJASRACが「著作権侵害」と裁判所に提出したことによりこの問題が始まる。
JASRACの言い分はこうだ。
「お前はJASRACにこの曲の権利を譲渡してるのだ。お前の曲ではない。この曲はJASRACの曲だ」
裁判が終わって私は、私ひとりが権利を持つ曲の全てをJASRACから引き上げる作業をしている。
だってこの曲は「私の曲」なのだから・・・そんな組織に預けるなんてもっての外だ!!
ところがこの楽曲に関しては引き上げられないと突きつけられた。
何故なら共作者のひとりが「JASRAC会員」であるからだ。
この「JASRAC会員」という契約は、私なんかは大昔に
「そうすれば得だよ」
と事務所の人かなんかに言われたそうしたような記憶がうっすらとある。
当時はJASRACが独占で、他に選択肢がなかったので別に気にしてなかったが、
今となってはこれはとんでもない契約内容である。
なにせ
「あなたが書いた曲は、その書いた瞬間から未来永劫JASRACのものですよ」
という内容なのだから・・・
私なんかは、自分の未発表曲を演奏しただけでJASRACに「著作権侵害」だと裁判所に提出された。
未発表であろうが、この契約があるのだから書いた瞬間にJASRACのものであるというとんでもない理屈だ。
私自身はもうこんなクソみたいな契約はその後解除したが、
まだ数万人の音楽家たちが知ってか知らずか(きっとこんなことまでは知らないであろう)このようなご無体な契約を結んでいる。
今回問題になったのは、共作者であるお二人の師匠のうちおひとりが「JASRAC会員」であったので、JASRACから引き上げるなんてことはもっての外だというわけだ。
何故ながらこの曲は「お前の曲ではない、JASRACの曲」なのだから・・・
しかし私はこの楽曲を演奏してJASRACから「著作権侵害」と突きつけられた時に考えた。
もし私がお二人の師匠の作った部分を演奏してたとしたら、それはお二人の権利を侵害したことになるかも知れない。
でも私はこの「組曲」の自分が作った部分だけを演奏しているので、決して師匠お二人の権利を侵害しているわけではない。
そして今回の収録曲は「組曲」ではない。
自分の作った部分だけを演奏しているのに、JASRACは3人に印税を分配するぞと言っているのが現実なのである。
要は「組曲」なのに「一曲」のように登録しているから問題が起きるのだ。
「組曲」と言えば、有名どころではピンク・フロイドの「Shine On You Crazy Diamond」という曲は下記のように一曲が別々の曲のようにJASRACに登録されている。
イントロ1 (Pert1として別曲として登録) 作品ID:0S1-9536-4
イントロ2 (Pert2として別曲として登録) 作品ID:0S2-0134-8
イントロ3 (Pert3として別曲として登録) 作品ID:0S2-0135-6
テーマ部分 (Pert4という別曲として登録) 作品ID:0S2-0136-4
歌~エンディング (Pert5として別曲として登録) 作品ID:0S2-0137-2
(各パートがイントロなのかテーマなのか等はこのウィキペディアを参照にしました)
弁護士に相談してみたところ、
著作権法上、楽曲が
① 共同で創作され
② 分離利用が不可能
であれば、一体不可分な「共同著作物」と扱われます。(2条1項12号)
これに対し、楽曲が上記①と②のどちらかでも満たさない場合には、それぞれの部分が独立の著作物になります。
つまり、3個のパートが別々に創作されていたり(上記①)、3個のパートが分離利用可能だったりすれば(上記②)、それは単に独立の3個の著作物が集まっているだけ(集合著作物)と判断されます。
ということなので、私(と共作者による)の「天界への7番目の扉」という「組曲」の場合、分離利用可能(②)であり、それぞれの部分の作曲者は下記の通りである。
0~4:00:7拍子部分(ファンキー末吉作)
4:01~8:00:オーケストラ組曲部分(お二人の師匠作)
8:01~11:02:7拍子部分(ファンキー末吉作)
「分離可能」も何も、途中でテープ(当時はアナログ録音)を止めて録り直してるので、この部分には唯一空間があり、物理的に「分離」している。
それに対して、ピンク・フロイドの「Shine On You Crazy Diamond」なんか隙間もなければウィキペディア見なければどこが曲の変わり目かもわからない「分離不可能」であるのにJASRACは「組曲」として登録を受理している。
要は私は「天界への7番目の扉」をこの「Shine On You Crazy Diamond」のように「組曲」に登録し直したいわけである。
「分離不可能」なピンク・フロイドの曲をこうしてちゃんと分離して登録しているのだから、明らかに「分離可能」なこの「組曲」をこのように登録することが出来ないわけがない!!
上記3つの部分をそれぞれピンク・フロイドのように
天界への7番目の扉Part1
天界への7番目の扉Part2
天界への7番目の扉Part3
という別々の曲として登録して、今回のJazzアルバムには「Part1」を収録ということにすればよい
・・・と言うか、もともとそうするべきだったのだ。
それをしていなかったがために裁判であんな酷い目に合わされたわけだ。
まあここまで理論武装していれば大丈夫だろう・・・と、
これが音楽業界のややこしいところなのであるが、JASRACではなく権利をお預けしている出版社を通してJASRACにお願いすることになる。
ところがその出版社に対してJASRACが送った返事は・・・「NO!!」!(◎_◎;)
もうね、想像するに慇懃無礼にNOと言う彼らの語り口調が思い起こされて来てカチンと来たが、私が怒っては間に立っている出版社の人が困るわけだから、このシステム、JASRACにとっては非常にうまく作ってやがると思うしかない・・・
グッと堪えて出版社と温和に(出版社に何の罪もないので温和にするしかない(涙))話し合い、
結局、今回このJazzアルバムに登録する曲を「別名登録」することしかなかろうという結論に達した。
出版社の返信によると、
「天界への7番目の扉」の一部であるファンキー様作曲部分を、「子曲」として別曲扱いで届出する形での変更を受け付けるかという点については、検討の余地はあるとのこと
だそうで、「検討の余地はある」という言い方に非常にカチンと来るけれども、
ここで怒ったら間に立っている出版社の方に迷惑をかけてしまうのでじっと我慢する。
更にはこのような条件も突きつけられる。
・共作者の同意書等をご提出する必要がある
まあこれは共作なのだから当たり前である。
既に師匠お二人には承諾を取ってある。
・同じ出版社が管理をすることが前提
(※親曲と子曲で別の事業部が管理するというのは不可、とのことです)
まあ、本当はJASRAC管理楽曲から外したいのだが、他の楽曲も無理言って外させて頂いている手前、揉めに揉めたこの楽曲をそのままこの出版社にお預けすることはやぶさかではない。
ところが最後の一文にまたカチンと来た。
・子曲には「天界への7番目の扉Part1」というよりは使用者も明確に別曲であることが
判断できるような別のタイトルをつけて欲しい
JASRACにはもっと紛らわしい名前の曲がいっぱいあって、
それを間違わないようにちゃんと分配するのがJASRACの仕事じゃろ!!
そもそも別曲ではなく「子曲」にしろと言いながら、
「似たタイトルは認めん!!別のタイトルにしろ!!」
というのは全く道理が通らんじゃろ!!
だいたいJASRACという会社は何の「音楽的」な仕事をしているわけではない。
タイトルと作詞作曲家でデータベースを作ってそれに照らし合わせて徴収と分配(この部分は相変わらず不透明なのだが)をしている会社でしかない。
例えて言うと、ドメインを管理している会社が、
「このドメインは既に使われてますので」
と言うならわかるが、
「似たドメインにしないで下さい」
などという権利があるか?!!
まあいい、私が怒れば間に立っている出版社の方が困るのだ・・・
腸が煮えくり返りながら別名を色々考える・・・
実はこの「天界への7番目の扉」というタイトルには大きな「意味」がある。
アルバム「亜州鼓魂」の中では、次に続く黄家駒への追悼曲、それにたどり着くまでに7つの扉があり、それを「7拍子」とかけてこの組曲にしているのだ。
当時、日本ではロックのイメージが強すぎて、誰からも興味を持ってもらえないJazz活動を、黄家駒がそのライブを見に来てこう言った。
「凄いよ!全くもって凄い!!毎月やってるのか?次も絶対に見に来るから!!毎回必ず見に来る!!」
それが黄家駒が私にかけた最後の言葉となった。
Jazzとかを演奏していると、時々トリップして自動書記のように勝手に身体が動いている状態になる時がある。
まるで真っ白な世界を漂っているようなそんな状態である。
そう、黄家駒が死んだ時にWingが卒倒して私の腕の中に倒れ込んで来て、
うわごとのようにこんなことを言っていた。
「は、は、は、あいつはさぁ・・・今、真っ白なところにいるんだよ。
とても気持ちいいんだって、酒飲むよりもセックスするよりももっと気持ちいいってさ、は、は、は」
私は「その世界はある」と思った。
それは私たちプレイヤーが「偶然」物凄い演奏をした時に訪れるあの「真っ白な世界」と同じなんだ、と。
そして私がその世界に続く扉を開ける度に、黄家駒は最後の扉のところにいて私の演奏を聞いている。
そう、あの日の「約束」通り・・・
だから「天界への7番目の扉」なのだ。
その名前を変えろとは・・・(怒)
いかんいかん、怒れば間に立っている出版社の人が困る・・・
だから頑張って我慢して別タイトルを考えた。
第一希望:The Door to 7th Heaven(カタカナ表記:ザドアトゥーセブンスヘブン)
「天界への7番目の扉」とは全く違うタイトルです。
第二希望:The Door to Seventh Heaven(カタカナ表記:ザドアトゥーセブンスヘブン)
それでも紛らわしいというなら表記を変えます。
第三希望:7th Door To Heaven(カタカナ表記:セブンスドアトゥーヘブン)
これは「天界への7番目の扉」の英語表記として登録されているので却下されるかも知れません。
(どうしてこの団体が曲名を却下する権利があるのか?!!(怒))
第四希望:7th Heaven(カタカナ表記:セブンスヘブン)
譲歩もここまでだと思います。
Seventh Heavenというのは有名な慣用句で、これを使った曲タイトルは無数にあります。
(代表的なのはマイルスデイビスのSeven Steps to Heaven)
ちなみに「7th Heaven」も私のやってるバンド「X.Y.Z.→A」の曲名でもありアルバムタイトルでもあります。
というメールを送ったところで怒りは「沸点」に達した。
このような歌詞のないインストナンバーでは「タイトル」がすなわち「歌詞」と同じ意味を持つ。
それを「紛らわしいから」という理由で「この歌詞にはするな」とは、この人たちは一体何様だと思っているのだ!!(怒)
ついつい怒りに任せて次のような一文を出版社に送りつけてしまった。
「Seventh Heaven」というのは「天にも昇るような喜びの極致」という意味で、そこに入るドアということは「天界への7番目の扉」というのとは全く違った意味となります。
(天にも昇るような喜びの極致に入る1番目の扉ということになります)
ご指定の通り「全く違うタイトル」をつけておりますので。
それでも「変えろ」と言うのならここまで譲歩しますので、これで却下するようでしたら担当者の名前を教えて下さい。
訴訟します。
この「訴訟します」というのが聞いたのだろう。
JASRAC内部で
「あの人は本当に訴訟したりする人ですか?」
「いやあれは絶対にするだろう」
になったに違いない、しばらくしてから返事が来た。
別曲の方についても、「天界への7番目の扉」と同様、全支分権についてJASRACに預ける
という点が前提となるのですが、
そのような取り扱いで問題なければ、別曲の方のタイトルについて、ご希望通りの「天界
への7番目の扉Part1」というタイトルのままで問題ございません、とのご連絡をいただき
ました。
また親曲・子曲としてではなく、別曲としての取り扱いで可能とのことです。
激怒!!!
お前は一体いつの話を言っているのだ!!
お前らが「変えろ」と言うからスタッフと一晩がかりで考えて「The Door to 7th Heaven」にしたのだ。
また前に戻せと言うのか!!お前らは最新のメールを見とらんのか!!
怒ったらあかん怒ったらあかん。
怒ったら間に立っている出版社の人に迷惑をかける。
気を取り直して出版社の人にメールを送る・・・
すみません、そちらを振り回してしまうことになりますが、
元々JASRACが「天界への7番目の扉Part1」を却下したことにより大きく振り回されて、
また二転三転の後に元に戻ったことによりまた振り回されてしまったという現実があります。
自分が「変えろ」言っておきながら、結局待たされて「やっぱこれにしろ」と言われてもちょっと身勝手過ぎる感がありませんか。
出来ますれば、もう苦渋を飲んで「The Door to 7th Heaven」に決めた、という状況もありますので「The Door to 7th Heaven」で登録したいのですが・・・
ということで「こちらがお願いして」なんとかこのタイトルに「して頂いた」。
しかし今となってはこのタイトル、結構気に入っている。
「天界への7番目の扉」は前述のような「意味」があるのだが、
このタイトルの場合、もう6つの扉を開けて「7th Heaven」、
つまり黄家駒のいるあの世界に続く最後のドアのところにいるような意味合いがある。
黄家駒は天界でこの演奏を聞いてどう思ってくれるだろうか。
「凄いよ!全くもって凄い!!次も絶対に見に来てやるぜ!!」
とまた言ってくれるのか、それとも
「まだまだな」
と最後の扉を開けてくれないのか・・・
まだまだ6つ目の扉まで来てないかも知れないし、
7つ目なんかまだまだ開けられるものじゃないかも知れないが、
こうしてここまで来た!!
ここで扉が開かなければまたもの凄い演奏をして開けてやる!!
今は「ここまで来た!!」・・・それがJazzである。
戦いは一生続くのである。
配信サイトでは試聴が出来たりするので、
ちらっと聞いてもしよかったら末吉の戦い・・・
こんなアホみたいな組織との戦いではなく、天界へと昇るための戦い・・・
に耳を傾けて頂ければ幸いである。
Posted by ファンキー末吉 at:10:00 | 固定リンク
2018年12月22日
クメール語版「中国のマドンナ」
このアルバムに収録される「中国のマドンナ」という曲(DEMO音源21:40から、ライブ音源20:25から)は、他の国のバージョンでは「別にシチュエーションは黄河のほとりとか中国でなくてもいいよ」と言っている。
カンボジアのくっくま孤児院に着いて、車座になって「どんなシチュエーションにする?」と話し合った。

まずは「君たちがね、将来好きな人が出来て、結婚して住むとしたらどんなところがいい?」と聞くところから始まる・・・
バンドの4人の意見はだいたい同じだったようで、やはりそこはプノンペンのような都会ではなく、小さな田舎の村だったようだ。
「川のそばの小さな村の中の小さな家」というのがこの曲のテーマである。
みんなどんな村を想像してこの詞を書いたのだろう・・・興味津々である。
実際にそのイメージを詞にするのは主にボーカルの子。他の3人は意見を言ってこの子が詞にまとめる。またこの子がちょっと言葉探しなど迷った時にはみんなに意見を聞いているようだ・・・
作詞ちう〜 - Spherical Image - RICOH THETA
座って書いてたのだが、だんだん熱が入って寝そべって来る・・・(笑)
出来たら歌ってみる。
ここからはボーカルだけの作業で、他の3人は心の中で声援するのみ・・・

ここでワンコーラスだけだが一応最初のバージョンが完成するのだが、「詞を直したい」というので、残りは翌日に持ち込んでこの日は終了!!
このような前向きな意見が出るということは素晴らしいことである。詞のレベルが上がるだけではなく、詞にどんどん思い入れが詰まってくる。
終了後は孤児院のみんなと一緒に差し入れのスキヤキをみんなで食べる〜・・・ちなみに生卵はイオンプノンペン店で生食用のを買って来ました。牛肉は一応25人分買って来たつもりだが、英語塾に行っている8人の分もほぼ全部食べちゃった・・・(笑)
さて翌日に子供たちが学校から帰る頃を見計らって行ってみたら、うろ覚えだったメロディーも完璧に覚えていて、詞の直しも終わっていた。
つるっとレコーディングして2番を作っておしまい!!
演奏するのは簡単な曲なので、イントロとかをバンド用に作ってあげて簡単なバンドアレンジをしてあげる。
なぜかと言うと、この子たちは先日も結婚式に呼ばれて演奏するという「仕事」に行って来た。
カンボジアでは結婚式は延々4時間とかずーっと演奏しなければならないらしく、これはバンドとしては「出口」があるなと考えてのことである。
日本のバンドから「僕たちデビューしたいんですけどどうやったらデビュー出来ますか?」と聞かれることがあるが、こっちが聞きたい!!(笑)
日本はひと握りのレコード会社と音楽プロダクションが全てを牛耳っていて、そこに辿り着かないとあとはインディーズしかない。
インディーズも、ライブハウスは基本自分で客を呼ばねばならない訳で、ここから顧客が広がってゆくということは夢のまた夢である。
カンボジアの音楽界もきっと一部のトップの人たちだけで回っているのだろうけど、見知らぬ大勢の人の前で演奏出来るチャンスが多いということは、彼らのように「何も持たない」人たちにとっては大きな「出口」だなと思ってのことである。
4時間も演奏するのだから、このようなオリジナル曲を演奏したっていいだろうし、この曲の設定の村を新郎新婦の村に変えるだけで、新郎新婦への大きなプレゼントになる・・・

彼らは孤児なので当然音楽教育など受けたことはなく、見様見真似で楽器を弾いているだけと言うが、なかなかどうして飲み込みも早く、一瞬でバンドバージョンが出来上がった。
さて前日の歌入れの時にも思っていたのだが、もともとこのオケがあって、それに合わせて歌っているだけなので仕方がないのだが、この子にとってはこの曲のキーはちょっと低いようだ・・・
ちゃんとキー合わせをしてみる。
もともとCのキーなのだが、Dぐらいまで上げてあげるのがよさそうだ・・・
というわけで、バンドのみんなにはこれは「宿題」。さっき演奏したものをDのキーで出来るようにして、間奏も自分でいいメロディーを考えて完成させて下さい〜
それにしてもこのボーカルの子はずーっとリーダーシップを発揮していて、さすが「歌手になりたい」という夢を持っているだけのことはある・・・
彼女から送られて来たお手紙
オケのキーを機械で強引に変えて彼女にもう一度歌ってもらった。
もうメロディーもちゃんと頭に入っているのでつるっと2回歌ってもうOK!!
ホテルに帰ってデータを編集して簡単なMTVにしてあげた。
これを作りながら何故か彼女の歌と可愛らしさに涙が出て来た・・・
いや、本当に「歌手になる」どころか、ヘタしたら「カンボジアで一番のスター」になれるかも知れんぞ・・・(ブログ「希望の星になれ」)
この子たちははたしてどんな村のどんな小さな家を思い浮かべて詞を書いたのだろう・・・
そして将来はどんな伴侶を見つけてその描いたような生活をするのだろう・・・
この子たちがこの日に思い描いた通りに、幸せな人生を歩んで欲しいと心からそう願う。
この曲はオケは既に完成。クメール語版の本チャン歌入れは来年、そして日本語版の歌は年末に入れる予定です。
仕上がりをお楽しみに!!
よろしければクリックを〜
![]()
にほんブログ村
Posted by ファンキー末吉 at:17:02 | 固定リンク
2018年12月 4日
BEYONDの思い出の曲
黄家駒が生きてた頃は、ただ毎日一緒に飲んで遊んで、死んでから初めてBEYONDがこんなに偉大なバンドだと知った。
最初に愕然としたのがこの曲!!
AMANI
アイドルとして(?)人気絶頂の時にアフリカに行って戦争で焼け出された子供たちを慰問し、この反戦歌をヒットチャートに放り込んだんだから凄い!!
黄家駒の葬式の時だったか、
香港のどっかの広場でWINGと待ち合わせしてて、
なかなか来ないからひとりで開店寿司屋に入ってビール飲んでたのよね。
そしたらこの曲がテレビで流れて来てしかも字幕付き・・・
戦争の影でいつも傷つくのは
何の力もない子供たち
僕は歌うよ!!
以下AMANIのからの一節はスワヒリ語で「愛、平和、僕たちに力を」
もうね、ちょっと前に死んだ人間が
「僕は歌うよ!!歌い続ける!!」
と歌ってんだから、ひとりで号泣!!
ビールが日本酒に変わり、泥酔して葬儀に行った・・・(笑)
ところでこの曲の日本語バージョンがYouTubeにアップされてた!(◎_◎;)
あのね、これ私が作った日本語詞、夜総会バンドの音源なんですけど・・・(笑)
次にこれ!!光輝歲月!!
神に召された黒人の追悼曲で、
「彼の人生の意義は皮膚の色による差別との戦いだった」
とか
「虹が美しいのはそれぞれの色が分かれてないからだ」
とか、もう涙・・・(号泣)
もうこの辺は大スタンダードで、中華圏の酒場だけでなく、
タイのパタヤビーチやチャン島の箱バンまで演奏してた定番曲ですな!!(凄っ)
そして最近お気に入りなのはこれ!!
「理想よさようなら」と来て、最後には
「共にRock'n Rollと高らかに叫ぼう!!」
ですからもう涙が止まりません!!(号泣)
Rock'n Rollと言えば、人差し指と小指を立てたロックピースサインを初めて見たのは黄家駒の葬儀の時だった。
葬儀場から棺が運ばれる時に、道という道を埋め尽くしたBEYONDファンがみんな、このロックサインを掲げて泣きながら「BEYOND!!BEYOND!!」と全員で連呼していた・・・(涙)
そう、BEYONDは偉大な「ロックバンド」だった。
黄家駒は死んで「ロックの神様」になった。
その精神を残された私たちが継承してゆく・・・(まだ道半ば)
黄家駒の遺作となったこの曲
なんかを叩く時はいつも泣きながら叩いている。
「ドラムを教えてくれ」という中国人にはいつもこの曲を例に取ってこう言う。
この曲のな、間奏に入る前には今まで押さえつけてたものを全部解き放つかのようなオカズを入れるんだけど、間奏に入った瞬間にはちょっとだけ力を抜いてやるんだよ。
それが「悲しさ」を表現する・・・
「世の中にはどうしようもないことがあるんだ」
そんな気持ちをドラムで表現しながら天と会話するのだ。
この曲なんかも思い出深い・・・
これはBEYONDというよりWINGとの思い出・・・
思えば彼が一番どん底の時・・・
ドラムをやめて歌を歌い始めた彼が、
広東省の酒場でギターを弾きながらこの曲を歌ってた。
「何でバンドじゃないんだ!!バンドだったらどんなど田舎にも俺がドラムで一緒について行ってやるのに・・・」
などと思ってたら、十数年後にはWINGバンドで一緒にワールドツアーを廻っている(笑)
そして今度はPaulも一緒!!
あと2回リハーサルしたらマカオでコンサート!!
その後は広東省と四川省、タイとマレーシアとシンガポールが決まってます!!
今回3回も香港に往復してリハをやるスケジュールも含めて全部すっぽり合間に入ったけどさすがに広東省はスケジュールがぶつかった(>_<)
あとアメリカとカナダも行くんやと・・・スケジュール合いますように!!