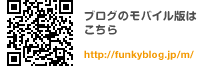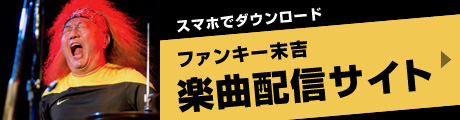
2018年8月30日
希望の星になれ!!
「縁」というのはそもそもがこのようなものなのかも知れない・・・
この商売、「休みを取る」という感覚がない。
スケジュールがぽっかり空く時、それが「休み」である。
最近は北京でいる時よりも中国のどっかの地方都市でいる時の方が多いので、
その最後のスケジュールが終わってその後にスケジュールが入ってなかったりしたら、
「ムズムズ・・・どっか南の国に行こうかな・・・」
などと考え始める・・・
いや別に日本に帰ったっていいのだが、
往々にして日本への航空チケットは高い(>_<)
というわけでいつもその時々で一番チケットが安いアジア諸国を探すのだが、
それが今回はたまたまカンボジア!!
何と上海から往復で3万円ぐらいで来れたのだ\(^o^)/
プノンペンに着いて真っ先に前回ドラムを叩いたバーに行ってみたのだが、
なんと白人がカントリーを歌う店になっててがっかり(>_<)
他に生演奏をしてるバーはないかと探したが、
この日は月曜日なのでライブは休み(>_<)
しゃーないなぁ・・・と、ふと考える・・・私は一体何をしたいのだろう・・・
前回はドラムを叩いて楽しかった。(映像)
まあ「休み」なのに「仕事」であるドラムを叩くのも変な話だが、
「趣味」でもあるのだからそれは仕方がない・・・
まあドラムが無理なら、カンボジアにデスメタルのバンドがあるみたいなのでそれを探してもみたかった。
ポルポトの大虐殺の子孫がどんなデスメタルをやっているか興味があったのだが・・・
まあそんなこんなで初日は何の収穫もなく、ホテルのプールサイドでぼーっとしてたのだが、
何やらタイムラインに色んな人から書き込みが・・・
「プノンペンで日本人が運営している「くっくま孤児院」のお子さん達が「くっくまバンド」というのを組んで一生懸命練習しています(^^)機会がありましたらぜひ」
まあええよ、ヒマやし(笑)・・・そしてこれこそが「縁」だったのである。
何の期待もなく、ただヒマであるからということで向かったこの孤児院、
まあ一応ドラムセットはあるだろうということで、「ひとりドラム」が叩けるような準備だけはして行った。
まあどこでどんな状況で叩こうがやることは一緒なのでそれはまあいい。
問題はその後に彼ら達の演奏を聞かせてもらってびっくりした。
!(◎_◎;)・・・いい!!この音楽、むっちゃいい!!
聞けば彼らは当然ながら孤児なので音楽教育を受けたこともなく、
耳コピで見よう見まねで弾いているだけだそうなのだが、
この演奏が私の心を鷲掴みにした。
思えば1990年に初めて北京に行った時、地下クラブで偶然見た黒豹のライブ、
当時の稚拙な彼らの演奏から口ではうまく説明出来ない「何か」を感じて、
そしてその後の自分の人生が全く変わってしまって今も私は中国でいる。
同じような「何か」をこの演奏から感じ取った。
黒豹はその後中国ロック界の重鎮となったわけだが、
この子達にも「何か」を感じる・・・
実はこの子達とはまた別の小さな縁があった。
秋に日本語の歌を歌うイベントがあるらしく、
この子達が今練習している曲が偶然にも「Runner」。
この子達が歌ってくれる「Runner」を聞きながら不思議に思う、
「こんなこともあるんだなぁ・・・」
たまたま慰問に来た人間が、たまたまその時に練習してる曲の作曲者だっただなんて・・・
園長さんはこの曲を作ったのが私だということは知らなかったので、
「実はこれ・・・私が作曲したんです・・・」
と言ったら、子供達が私にこう言った。
「すごーい!!(◎_◎;)作曲ってどうやってやるんですか?!!」
その時に私は心に決めたのだ。
「俺が何でも教えてやる!!」
北朝鮮で「ロック」を教えて来た人間である。
カンボジアでこの子たちに何を教えるなんて私にとってはしごく簡単なことである。
Facebookの私の投稿を見て、ある人がこう書き込んだ。
「いよいよカンボジア編スタートですね*\(^o^)/*」
「北朝鮮プロジェクトに続いて」という意味なのだろう。
私はこう返信した。
「北朝鮮に比べたらはるかに障害は少ないですよ(笑)」
映像に立派な演奏機材が映ってるのを見て、後々
「なんだ、この子達は恵まれてるじゃないか。他にもっと大変な孤児院はいっぱいあるのに」
などと言う人が現れるかも知れないので先に言っておこう。
私はこの子達から演奏機材を取り上げて別の孤児院に回せばいいのではなどとは考えない!!(キッパリ)
そもそもが、この子達に小さい頃から伝統舞踊を教えたこの孤児院の創設者が素晴らしいのだ。
「貧しい人に食べ物を与えるのが援助じゃない。釣竿を与えて釣り方を教えて、その人達が自分の力で食って行けるようにすることが大切なんだ」
と言った人がいたが、その通り、この子達は実際に伝統舞踊を踊ったりして収入を得ている。
まだまだ日本などからの支援の額には及ばないが、
それでも「自分で食ってゆく」何らかの「技術」があることは素晴らしい!!
他にも困っている孤児院はいっぱいあることも事実だろう。
でも私は「たまたま」この子達と知り合った。
だからこの子達を先に援助する!!
そして私はこの日、こう心に誓った。
「俺がこの子達をカンボジアで一番の大スターにする!!」
そしたらこの子達は下の子達を食わせていけるというだけではない。
この子達がカンボジアの全ての孤児達の「希望」になる!!
何の才能も環境もない孤児が、頑張ってこんなに成功したんだ!!俺だって!!私だって!!
そう思ってさえくれれば、もう泥棒や売春なんかやらなくたっていい!!
「孤児がのし上がるにはもうなにも犯罪を犯すだけが選択肢じゃないんだよ」
そんな世の中になったとすればそれこそ「大成功」ではないか!!
人を助けるには「力」が要る。
でももしこの子達がそんな大きな「力」を手に入れたとしたら、
この子たちはきっとそんな恵まれない孤児のためにその「力」を使うだろう。
絵空事を言ってるのではない。
この子達には「何か」そんな「力」があるように思えて仕方がないのだ。
北朝鮮ロックプロジェクトが始まって最初に平壌に行った時、6月4日高等中学校軽音楽部の女の子達と初めて会って私はこう思った。
彼女たちの笑顔こそが「ロック」なんだ・・・
考えてみれば、カンボジアの孤児達であるこの子達こそが直接的な「ポルポトの被害者」ではないか!!
だからこそ思うのだ。
この子たちの笑顔こそが「ロック」なんだ!!と・・・
老い先短いこの私が生きてる間にどれだけのことが出来るかわからんが、
たとえ私がいなくなっても、
たとえこの年長組の子達が就職したり結婚したり、バンドが出来なくなっても、
その下の子達がその「夢」を引き継いでゆけばそれでいい。
そしていつかこの国の「希望の星」になってくれればいい。
いつまでも「笑顔」で頑張って欲しい・・・
よろしければクリックを〜
![]()
にほんブログ村
Posted by ファンキー末吉 at:09:33 | 固定リンク
全中国ひとりドラムツアー2018年湖北省「襄陽」
だいたいにしてどう読むのすらわからん(笑)
襄陽(Xiang1 Yang2)「シャンヤン」と読むらしい・・・
着いてみて初めてわかる、湖北省なんや・・・(笑)
例によって担当者のShaは来ないらしい・・・
また見知らぬ土地にひとりで放り込まれ、見知らぬ人と飲んで仕事をするのだ・・・(笑)
ドラムの活動のため襄阳(どこや?笑)に着いた〜どこかと思ったら湖北省なのね〜料理が辛い!\(^o^)/ 諸葛孔明が暮らしてたところで三国志の桃園の誓いもこの辺だとか・・・へ〜 - Spherical Image - RICOH THETA
地元の鄭老師の言うことにゃ、この街は三国志演戯の諸葛孔明が暮らしてたところで、あの有名な「三顧の礼」が行われたところらしい・・・
まあドラム叩くには全く関係ないけど・・・(笑)
この辺の名物は「牛雑麺」!!
イスラム族も多く、新鮮な牛を使って辛い辛いそれは辛いラーメンである・・・
地元の人は朝からこれに「黄酒(HuangJiu)」と呼ばれる度数の低い酒を飲むらしいが、そのまま午前にドラムクリニックやって午後には命がけでドラムを叩かねばならんのでこの日はご遠慮した。
さてドラム教室でクリニックやって会場へ行くのかと思ってたら、
クリニックも会場でやるらしい!(◎_◎;)
着いたら生徒たちはもう来ていて、ドラムセットも並べられているが、
細かいセッティングは生徒たちの目の前でやることとなる・・・
セッティングが終わり、伴奏データを流すべく、エンジニアの人に
「モノで出しますのでDIありますか?」
と聞くと、
「そんなものはない。使ったことない」
ふむふむ、まあそんなこともあるので、
「じゃあメスで出しますんで、長いギターシールドあったらそれをミキサー卓に突っ込んで下さい」
「そんなものはない。ミキサーの入力はキャノンしかないので無理」
!(◎_◎;)
まあ生徒達も待ってるので細かいことは置いといて、
とりあえずその辺に転がっていた拡声器に繋いで音出してドラムクリニック開始!!
無事に終わった後で、
「じゃあ今チューニングして本番のセッティング終わらせとけばそのまま本番まで動かしませんから」
ということになる。
ふむふむ、じゃあ・・・というわけでチューニング開始!!
この日のドラムセットは多点セットで、
チューニング終わりにマイクを立てようとしてたエンジニアが私にこう聞いて来る。
「Funkyさん、一番よく使うタムはどれですか?」
???・・・マイクが足りないからどれかのタムだけマイク立てて後は立てない???
・・・そんなことしたらまるで「サ行とハ行だけ音抜いて喋ってみぃ」みたいなもんで、何喋ってるか聞き取れないでしょ!!
このぐらいの小劇場だったら一番後ろまで生音で届かせるから、
マイクは取り敢えずバスドラひとつとオーバーヘッドだけでいいよ・・・
「そんなんじゃ細かいニュアンスまで拾えないでしょ」
えーい!!うるさい!!タムひとつだけ拾われるぐらいならこっちが全然マシなの!!
この頃からなんとなく「このエンジニアとはソリが悪いな」と思い始めてくる・・・
何やらちょっと「プライドが高い」のだ・・・
まあ共産主義の名残りで、こういうタイプの人はたくさん見て来たので気にしない。
まあ最悪は生音!!ドラムは叩いたら必ず音が出るのでいいが、
問題は伴奏データをどうやって出すか、である・・・
「キャノンしか入力がないんだったら、子供達の伴奏はどうやって出してるの?」
見れば卓の横にパソコンを置いて、そのステレオミニプラグをキャノンに変換するコードで接続している・・・
「じゃあ子供達の演奏終わったらこのケーブルをドラム横に置いて、そこからキャノンで卓に繋いで下さいな」
もうこれだけのことをさせるだけで大変(笑)
まあ中国あるある、ワシは無事に外に音が出てドラムが生音ででもちゃんと出ればそれでいいのよ・・・
「じゃあサウンドチェックを始めましょう。バスドラ踏んで下さい」
ドンドンドン、いつものようにサウンドチェックを開始したら、
「なんですかこのバスドラの音は、なんとかなりませんか?
・・・ってお前、ドラムの音色にも口出しすんのか?!!
DIの存在すら知らない、「そんな物を使うことはないので必要ない物だ」まで言い切る人にドラムの音色にまで口出しされてちょっとキレる・・・
「このマイクはMC用のワイヤレスでしょ。だからですよ!!」
だいたいバスドラのマイクもオーバーヘッドのマイクも同じコンデンサーマイクで、それもワイヤレスって・・・(笑)
まあバスドラのフロントヘッドの穴の外にあるマイクをもっと中に突っ込んだ方がちょっとはマシになるだろうとマイクを動かそうとしたら、
そんな私を阻止して、
「知らないんですね、これはドラム専用のマイクですよ」
・・・もうね、かなりキレた!!
DIの時にも
「そんな物を使うことはないので持ってなくて当然だ」
みたいな物言いに、
「お前なぁ・・・俺がこの国で50箇所以上同じやり方で廻っててなぁ・・・」
まで言って、
「そんな程度の低いこと言ってんのはお前だけだぞ!!」
を飲み込んで言わなかったのだ。
中国人とケンカしたって何もいいことはない。
相手のプライドを立ててやることはこの国で仕事をするのに一番大切なことである。
「ケッ!!」
私は後ろを向いて、苦笑いをした。
「ドラム専用マイクだって・・・笑っちゃうよな・・・」
私はさぞかし嫌な顔をしてただろう、でも思い直して笑顔で振り向いた。
「じゃあこれで本番よろしくお願いします〜」
イヤなことは忘れてホテルに帰ってちょっと休み、
そして本番!!
「襄阳首届鼓手节」・・・なるほどね、「第一回襄陽ドラムフェスティバル」ね・・・
そう言えば鄭老師、
「初めてやるんで色々わからないことが多いんでよろしくお願いします」
と言ってたなぁ・・・
まあ段取り悪いのは今までも結構あったし、
音さえ出ればそれで何とかなるでしょう〜
「モニターがね、子供達のドラムの側にないでしょ。
これだと伴奏の音が聞こえなくてオケとどんどんズレちゃうからね」
サウンドチェックの時にそうちゃんと言ってあげてたのに、
本番ではやっぱり聞こえないのかちゃんとリズムがズレてる(>_<)
鄭老師、ステージの上からミキサーに
「すみませんが子供達のモニターを上げて下さい」
と言うが状況は変わらない。
モニターがステージの一番前にあるからよ〜(>_<)
遠過ぎて聞こえないのよ〜
シールドが短くて場所が動かせないので、結局子供達はそのままの状況でやるしかない。
まあ色んな場所で数多く見て来た現象である。
頭打って初めてわかる。来年にはちゃんと個別にモニターを用意するでしょう(笑)
さて子供達の出番が終わって私の出番!!
ミキサー卓からシールドを持って来てもらって繋ぐ。
モニターなんか要らない!!
何度もそんなことがあると一切モニターなんかに頼らない!!
イヤホンでクリックも伴奏も全部聞くし、
最初に演奏する曲は伴奏の音が先に先行して流れる曲にしてある。
ドラムと同時に始まる曲だと、外にちゃんと伴奏が出ているかわからんしね。
一度ずーっと伴奏が出てなくて1曲最後までドラムだけで叩いてたらしいし、
長いリズムソロやなぁ・・・(笑)
ついでに言うと、電源が必要なシステムも使ってない。
全て電池である。
ある時は電源引っこ抜かれて伴奏止まったもんなぁ・・・(シミジミ)
伴奏を出す、イヤホンをちょっと外してちゃんと音が外に出てるか確認、
出てる、イヤホンを直して待機、クリックが始まってそこから演奏開始!!
別に何の問題もない!!全く人に頼らないシステムである・・・
MCを挟んで2曲目、今度はクリック聞いてからドラムと伴奏が同時に始まる。
あれ?・・・ちょっと異変を感じて伴奏を止めてみる。
クリックが外に出てるやないの!!(>_<)
子供達はクリックがない音源をステレオで流すので、
サウンドチェックの時に
「右側だけ流すんですよ。左側はクリックなんでミュートして下さいよ」
とキツく言ってたのに忘れてるし〜(>_<)
ということは1曲目はずーっとクリックも外に流れてたのね・・・
まあ伴奏が流れてないよりはええわ(笑)
クリック外に流さないようにお願いして2曲目!!
まあドラマーは永遠に自分の外音をリアルタイムに自分で聞くことは出来ないので、私が出来ることはここまでである。
命がけでドラム叩いてそれで終わりである・・・
息も絶え絶えにステージを降りて、ステージ袖でびしょびしょのTシャツ脱いで汗を拭いている私を鄭老師が目を丸くして見ている。
「この人、飲んでる時は楽しいけど、こんな凄い人だったんだ・・・」
そんな視線である。
「子供達と一緒に写真を撮ろう」
ということになって記念撮影。
例のエンジニアがすっ飛んで来て、子供達を押しのけて
「老師!!私と一緒に写真撮って下さい!!」
(笑)
自分の子供をステージに上がらせて他の子供を押しのけて私と記念撮影までさせている(爆笑)
態度がここまで180度変わると面白いな(笑)、
打ち上げにまでやって来て一緒に酒を飲んだ。
昼間のわだかまりは酒と共に全部飲み干した。
これでいいのだ・・・
打ち上げなう〜 北京でもよく食って大好きなイスラム料理〜この街には回族が1万人ほどいてイスラム料理も美味しいとか・・・ でも北京で食うより倍辛い(>_<) - Spherical Image - RICOH THETA(端っこにいるのがエンジニアさん(笑))
ホテルまで送ってくれる途中、漢江の辺りで「孔明灯」を飛ばした。
昔諸葛孔明が通信手段に使ったんだと・・・
翌日は念願の「黄酒(HuangJiu)」と牛骨麺!!
三国志の英雄達もこの酒を飲んで天下を語ったのかなと想いを馳せた・・・
Posted by ファンキー末吉 at:07:07 | 固定リンク
2018年8月27日
中国ロックの叩き方
さて前回の黄绮珊(Huang QiShan)の次には、共に私がバックを務めた贝贝(BeiBei)という歌手の話・・・
一度彼女の新曲のプレスコンフェレンスに呼ばれてドラムを叩いたことがある・・・
曲のタイトルが「Young Rock Star」!(◎_◎;)
まあRockな喉を持って鳴り物入りでデビューした若いスターなのだからいいけど(笑)
デビューしたての新人歌手はオリジナルのレパートリーがそんなにないので、
新曲発表のプレスコンフェレンスとかならいいけど、30分とか演奏時間ではオリジナル曲が足りない。
必然的にカバー曲を歌うことになるが、その3曲が全て私が叩いてレコーディングした曲だった。
ますこの曲!!
名実共に一番成功したロック歌手のひとりである汪峰(Wang Feng)の曲。
(ちなみに嫁さんは大女優の章子怡(Zhang ZiYi))
毎回アルバムの時にレコーディングに呼ばれて半分以上の曲を叩くのだが、
この曲はこの時に叩いたのかこの時に叩いたのか、はたまた嫁さん連れて来たこの時に叩いたのか・・・
6/8のリズムでこれだけゴーストノート入れてたら中国の若いドラマーじゃぁなかなかコピー出来まい(笑)
案の定、贝贝(BeiBei)のライブ音源を聞いてみると、若いバンドのメンバーはかなり簡略化して叩いているようだ・・・
まあちょっとニュアンスが違って来るけれどもそれはそれでよかろう!!
大事なのは「スタジアムで叩いてる」感覚で叩いているかということだ。
これが若いドラマーには全く出来とらんぞ・・・
「武道館のステージに立ったことがあるバンドは違うね。
ライブハウスで演ったってオーラが武道館だもん」
と言われたことがあるが、
ステージとは「オーラを伝える」ところであるから、
「武道館ぐらいだったら一番後ろの席にも生音で届かせてやらぁ」
という「気迫」が必要である。
特にこの汪峰(Wang Feng)という歌手はいつもスタジアムで演っている人なんだから、
曲を聞いて、求められてるのはこんな感じだろうというのはすぐに伝わって来る。
特に3:18ぐらいからの間奏・・・
1:32からのドラム導入部分にも間奏があって、
これも初顔見世なので思いっきりテンションを上げて叩かねばならなかったが、
その後はAメロに入るので緩やかに落としてゆくけど、
この間奏はもうありったけのアドレナリンをぶち込んでテンションMAXで叩かねばならん。
私が電気ドラムを叩けないのは、
ただの「スイッチ」でしかないドラムパッドは、こんな時に押されるべき「根性ボタン」がないのね・・・
サビまで行って「フォルテ」まで持っていってたら、
その後のこの間奏は「フォルテ+根性」(笑)
もうアドレナリン出まくりで目つきヘロヘロ、ヨダレ垂れまくりで叩いてなくてはならない。
若い衆よ、お前はカッコばかりつけてるが、本当にヨダレ垂らしながら目がイって叩いたことがあるか?(笑)
そしてその後にはまたサビが来るので、そこで気が緩んではならない。
例えて言うと、生死を分けた戦いが終わって、
その瞬間に身体はまだそのまま戦ってるんだけど、
精神は両手を上げてガッツポーズをしてる感じ?・・・
ここでX.Y.Z.→Aだったら二井原が「イエィ!!」だとか「カモン!!」だとかシャウトをするのだ(笑)
ブースの向こうでは汪峰(Wang Feng)がこちらに向かって親指を立てる。
彼には見えてるのだ。
この部分で自分がスタジアムでどんな感情になって客がどのようになっているのかが・・・
ドラムはバンドの「指揮者」。
Funkyがそんな土台を作ってくれた。
あとの楽器はそれに合わせればいい。
自分はその全てに乗っかって歌うのだ、と・・・
この曲は細かいテクニックが色々あって説明に難しいのだが、
次の曲、これは簡単!!
要は「爆発力」である。
0:16や1:18秒からのこのサビの叩き方、
私の中にはこのようなフレーズはないので、
きっと若いプロデューサーの指定だったのだろう。
とにかくこれをアドレナリンばりばりでヨダレ垂らしまくりで叩く!!
要は「爆発力!!」これが欲しいから打ち込みのドラムでなくこのファンキー末吉を呼ぶのである!!
2:00ぐらいから次のAメロに向けて「落としてゆく」のだが、
そこからAメロは
「力を抜くんじゃねぇ!!タイトにするんじゃ!!」
という大切なことを語ろうと思ったらリズムBOXに差し替えられとるやないの!!(笑)
まあ機械にすぐ差し替えられるほどクリックに忠実であることも必要。
2000年頃最初に中国でスタジオ仕事をやった時、
そのプロデューサーが音楽仲間にその音源を聞かせて、
「これは機械ですか?人間ですか?」
と言われたという話を聞いた。
「機械のようなドラムですね」という意味ではない。
「人間ですよね、どうしてこんなに機械のように正確なんですか」
という意味である。
機械的なんてあり得ない。
「ファンキー末吉のドラム」というのはとかく「人間的である」ことであると思っている。
まあ「喜怒哀楽」が激しいんやろうな・・・
だから実際の生活でもそれで人とトラブる(>_<)
でもそんな性格のイビツさがドラムにもちゃんと出ている。
その喜怒哀楽豊かな表現が機械と完璧に同期していて、どの部分もリズムBOXに差し替えられ、もしくは両方生かせて使うことが出来る、
という部分も、私が中国ポップスのレコーディングに大きく貢献した部分のひとつだと思っている。
さてここまでは「喜怒哀楽」の「怒」であるが、
ここからが中国ロックの真骨頂!!
贝贝(BeiBei)がコンサートのラスト曲に選んだのはこの曲・・・
許巍という歌手は、
これも中国ロックの歴史に残る1枚であるのだが、『在別処』というアルバムを録音し、その後順風満帆かと思えばその後に北京の音楽界に失望して西安に帰る。
私はこの『在別処』のデモ音源を彼の部屋で聞かせてもらったことがある。
グランジ系のロックで「中国ロックもここまで来たか」と思った・・・
ここからは都市伝説だが、その後麻薬に溺れ、
禁断症状から抜け出すために家の入り口を釘で打ち付け、
自分で自分の身体を縛って(自分では縛れんじゃろ・・・笑)、
LuanShuがそのドアをぶち破って彼を助け(ぶち破れんやろ、普通・・・笑)
彼の縄を解いて彼を抱きしめた時に彼はこう言った。
「曲が出来たんだ・・・」
その曲がこの「蓝莲花(LanLianHua)」だったという・・・
「帰ろう!!一緒に帰ってアルバムを作ろう!!」
そう言ってLuanShuがプロデュースして作ったアルバムが、この曲が収録されている「时光漫步(ShiGuangManBu)」!
「メンバーは誰でもお前の好きなメンバーを呼べばいい。ドラムは誰にする?」
そう聞いたLuanShuに許巍は「Funkyがいい」と答えて、結局全曲私が叩くことになった。
そしてこのアルバムが中国ロックに金字塔を打ち立てるような大ヒットとなり、
私は今だに「許巍のドラマー」とよく言われる。
不思議なもんだ。
今では汪峰に録音した曲の方が多いはずなのに、「汪峰のドラマー」だと言われたことは一度もない。
きっと许巍の伝説のコンサートにいくつも参加してるので人々にはそのイメージがあるのだろう・・・
人々にはあまり知られてないが、
私の中で一番「伝説」のコンサートが、
アルバムが出来て最初のコンサート・・・
今ではスタジアムで演奏する彼だが、
その時は北京の小さな小さな小劇場で行われた小さな小さなコンサート・・・
実は私は前の日、全ての譜面を見ながらそれぞれの音源を聞いていて、
ある瞬間に彼の「詞」が流れるように頭に入って来た!(◎_◎;)
涙で譜面が霞んで来たのを覚えている・・・
コンサート当日、全ての曲のカウントを出すのは私だから、
曲つなぎかMCかを知っとく必要があったので出番直前に彼にこう聞いた。
「MCはどの曲とどの曲の間に入れる?」
それに対してキョトンとして彼はこう答えた。
「MC?・・・喋りなんか入れないよ。俺は歌いに来たんだ」
これもひとつの「中国ロック」の伝説である・・・
何曲目が終わったところだろう、
スティックをかざして次の曲のカウントを出す準備をしてたら、
ステージからいきなりいなくなった。
何も言わずにいなくなったのでこちらとしてはどうしようもない。
LuanShuも一瞬戸惑っていたが、うんうんと頷いて私に「待て」と指示した。
何分ぐらい待ってただろう・・・
5分?10分?・・・
何もアナウンスもせずに無言で待つ時間としてはとてつもなく長い時間だったのを覚えている。
だが不思議なことに、置いていかれた観客がひとりとして声を上げる人間はいなかった。
许巍のファンは熱烈である。
命がけで许巍を愛している。
そんな熱烈なファンが誰一人として騒いだりしなかった・・・
ステージ上のミュージシャンも客席の全ての観客も、
いつまでもいつまでも黙って许巍が帰って来るのを待っていた・・・
噂によれば「トイレで泣いてた」という都市伝説もあるが、
帰って来た许巍は何のエクスキューズもせずに、
何事もなかったかのように歌い始めて、
そして何事もなかったかのようにコンサートは終わった。
その打ち上げの席で偶然許巍の隣に座った私は、
昨夜の話、「突然歌詞が入って来たんだよ」という話から、
「どうして日本人から見たら構成がこんなに変わってるかと思ったら詞だったんだね」
という話・・・
そして最後にこう言った。
「わかったよ、お前の音楽が・・・
お前の音楽はなぁ、絶望の中で一筋の希望を見た、それを歌ってるんだろ?」
これには许巍自身もびっくりして、
「それ以上言わないで・・・俺・・・泣いちゃうから・・・」
また前置きが長くなってしまった。
では「絶望の中で一筋の希望を見た」という音楽はどうやって叩くのか?
これこそが「中国ロックの奥義」である!!
まずこの曲を聞いてみて欲しい。
「时光漫步(ShiGuangManBu)」の中に収録されている许巍の人気曲のひとつである。
そう言えばこのアルバムが発売された時、
突然黒豹のドラマーと零点のドラマーがこう言って電話して来た。
「感服しました。僕たちはゼロからもう一度あなたに学びます」
中国ロックの歴史の中で一番レコード売ったバンドのドラマーと、
中国ロックの歴史の中で一番金を稼いだバンドのドラマーにこんなこと言われるんだから大したもんである(笑)
スタジオ仕事なんか叩いたらどんな曲なのか全部忘れてしまうので、
それからこのアルバムをゲットして聞いたら、この曲のドラムに自分で感激した。
この曲が大好きになって、それこそ毎日毎日、何十回も何百回も聞いた。
聞くたびに思うのが、
「このドラマーはなんて悲しいドラムを叩くんだろう・・・」
ということである。
「このドラマーは、その人生でどれほどの絶望を味わったのだろう・・・」
などとも想像してしまう・・・
まあ自分の人生は自分がよく知っているので「絶望」でもなんでもない。
単に「喜怒哀楽」が人より激しいだけの話である(笑)
では物理的にどのようにその「哀」を表現するのか・・・
これは後で「そうなんだ」と思ったことであるが、
要は「力の抜き加減」である。
1:47からのサビ、
これまで押さえて来たものがもうすぐ全部爆発するぞ・・・みたいなフィルに続いて、サビに入った瞬間にふっと力を抜く。
それが「悲しい」のである。
レコーディングの時には詞など全くわかってなどいなかったが、
実は見事に詞とリンクしている。
「完美生活(完璧に美しい人生)」など「ありえない」のである。
同様に前曲の「蓝莲花(ハスの花)」も同じである。
中国には「どうしようもないこと」がたくさんある。
(中国でなくても実はたくさんあるのだろうが)
天安門事件で仲間を殺され、
中国共産党に目の敵にされてライブを潰され、
そして許巍のようにショービジネスの世界に絶望して故郷に帰ったり・・・
中国の同じ世界で生きて、中国の同じ空気を吸っている私にとって、
その「気持ち」は手に取るようにわかる。
だから叩けたのである。
ではなぜ力を抜くと「悲しい」のか・・・
それはその直前までに秘めている「爆発力」だと思う。
「スローボールは力のないボールではない」
という言葉があるが、同様に
「小さい音は弱く叩くのではない」
ということである。
つまり「力いっぱい命がけで小さな音を出す」のである。
この秘めた「爆発力」が「悲しさ」を生むのである。
「世の中にはどうしようもないことがいっぱいある」
というメッセージとなるのである。
当然ながら「爆発力」が大きいほど「悲しさ」が大きいということになるので、
音の大きなドラマーの方が表現力が大きい。
江川ほーじんが自分のアンプのことを語る時、
「デカい音を出すために大きなアンプを使ってるんじゃない、
綺麗な音を出すために大きなアンプを使ってるんや!!」
と言う。
容量の小さいアンプをボリューム全開で鳴らすより、
余裕のある大きなアンプのボリュームを絞って鳴らした方が、
同じ音量なら大きなアンプの方が音がいいのである。
それと同じ!!
最後に前述の「蓝莲花」の話・・・
歌詞ともリンクするが、許巍のコンサートで若いドラマーがこれを叩いているのを聞いたことがある。
もうね、どうしようもない(>_<)
「没有什么能够阻挡(もう何も阻止するものはない)」
という歌い出しから始まるこの曲は、
ドラマーが最初のシンバルをピシャンと何も考えずに叩いた瞬間に全てが終わってしまう。
強く叩くと詞の意味は「本当に何も阻止するものはない\(^o^)/」という意味になってしまうし、弱く叩くと「絶望の中の一筋の希望」さえもなくなってしまう・・・
その間のほんの一握りのチカラ加減、それ以外に「正解」はないのである。
「リズムとは初恋のようなものだ」
と言ったことがある。
強く抱きしめれば壊れてしまう、
弱く抱きしめれば逃げて行ってしまう、
この恋を失いたくなければ、命がけでちょうどいい強さで抱きしめ続けなければならない。
「命がけでちょうどいい強さで叩き続ける」のじゃよ!!
ほんの一握りの強さの違いで曲のメッセージまでガラッと変わってしまうって凄いでしょ。
ドラムなんて音程もコード感もない、
ただ音の強さと密度だけしかない楽器だけど、
それだけで詞のメッセージすら変わってしまうぐらい大切な楽器なのよ。
ドラムはバンドの「指揮者」!!
だから音楽に最大の「愛情」と、最大の「責任感」を持って挑まねばならん。
別に中国語が分からなくても出来ることである。
曲を作った人が、歌手にこのように歌ってもらいたい・・・
アレンジする人がこのように歌ってもらいたい・・・
「ドラムをどう叩くか」はそのメロディーやアレンジの中に必ず答えがある。
それを敏感に感じ取って、それを命がけで表現する。
それだけである。
・・・てなことを偉そうに言っておきながら、
実はこの日のコンサートの時、
この「Young Rock Star」がこの曲を最後に歌うっつうので、ついつい強く叩き過ぎちゃったのよね(>_<)
そこで「しまった」とばかり弱めたりするともっと目も当てられない。
即座に判断してそれよりちょっと落としたぐらいの自然な流れの強さにして、
結果的に
「私はYoung Rock Starよ!!もう何も私を阻止するモノはないわ!!」
みたいな曲になってしまった(>_<)
すまん!!許巍!!
まあこんな「バージョン」もあるんだということで許してくれ!!(涙)