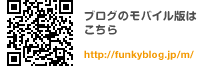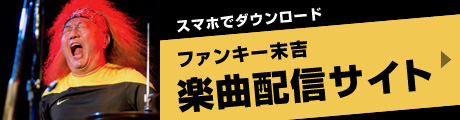
2014年5月14日
歌うということ
ひとりドラムツアーで対バンになったドラマーからいい質問も受けて、
久しぶりにこの「ドラムの叩き方」でテクニック的なことを書けると思っていたが、
昨日渡辺英樹さんの歌入れをしてて感じたことがあったのでまた精神論をひとつ〜
基本的にワシは歌入れが嫌いである。
自分が歌えんからっつうのもあるし、
歌をディレクションするっつうのはこれがむっちゃパワーいるのな。
ほんと歌い手さんと一緒に命削ってるっつう感じ・・・
ちなみに中国では歌のディレクション料はヘタしたらアレンジ料よりも高い。
そりゃそうやわのう・・・いい歌録れたらそれで歌手は大儲け出来るわけやから・・・
歌のディレクションにも大きくわけて2種類あって、
ひとつはどんな歌手でも自分の歌い方にディレクションする人と、
その歌手の持ち味を引き出してあげる人。
ワシは「自分の歌い方」っつうのを持ってないから必然的に後者。
もう「お好きに歌って下さい」っつう感じ・・・
初めてディレクションをしたのは李慧珍(Li HuiZhen)という女性歌手で、
彼女は「自由に歌いなさいなんてプロデューサー初めてです」と言ってたが、
結局そのCDは大ヒットして、後にワシに歌をディレクションしてくれという話も来たが、やっぱ無理!!っつうわけで断っている。
中国のプロデューサーで歌をディレクションしないってワシぐらいちゃうか・・・
二井原実がX.Y.Z.→Aのデモでワシが歌ったのを聞いて、
「いや、リズムはもちろんのこと、音程も全然外してないんやけど・・・お前のは歌じゃない!!」
と断言して下さった(笑)
さてここからが本題であるが、じゃあ「歌」というのは何なのか。
すなわち「歌う」ということは何なのかということである。
渡辺英樹さんの歌を今からエディットして・・・
(というより、もうそのままでOKなのぢゃが)
田川ヒロアキという恐ろしく耳のいいアレンジャーのところに送る。
ワシも英樹も緊張するのよね・・・田川くんのところに送るのん・・・(笑)
ちなみに田川くん、ギター入れしてる時に、
アンプのスピーカーのすぐ近くにマイクを置いて、
大音量でアンプ鳴らしてそのマイクの音を聞いているのにも関わらず、
「スネアのスナッピーが外れてませんよ」
と、ブースの隅っこに置いてあるスネアのスナッピーの音が聞こえて注意するという耳の持ち主。
ワシと英樹と、
「クーラーの音ってさぁ・・・普通問題ないよねぇ・・・」
と言いつつ、
「やっぱり消しときましょう」
と気を使う始末。
あ、また話が逸れたが、「歌う」という話・・・
英樹さんの歌がいいのよ・・・
何がいいと言うと、ちゃんと「歌ってる」のね。
何を歌ってもC-C-Bになる・・・(笑)
これはどういうことかと言うと、
「どんなジャンルを叩いててもファンキー末吉のドラムだね」
と言うぐらい凄いことなのですよ。
最近よく一緒にライブをやってるのでわかるが、
英樹さんの歌い方には大きくわけてふたつあって、
ひとつはロック的にガナる歌い方。
もうひとつはC-C-Bのヒット曲のように、
ちょっと甘ったるく歌う歌い方・・・
「お前50も過ぎて何甘えてんだよ!!」
と冗談では言うが、これが大きな個性となって「C-C-Bらしさ」を醸し出しておる。
つまり「武器」やな。
ドラムで言うとフレーズとか叩き方とか、いわゆる「テクニック」。
ワシの歌で言うと、この「テクニック」を一切持ち合わせてないので、
いわゆる「棒歌い」、ただリズムと音程が合っているだけでしかないから、
「これは歌ではない」と言われるのである。
いわゆる「表現」である。
これがないと「音楽」にならん・・・
英樹さんの場合、ある時はガナって歌い、語尾になるとちょっと力を抜いて甘ったるくシメたりする。
まあもちろんこのふたつの武器だけではなく、
ある部分は息を多く吐いて歌ったり、
またある部分は喉をシメて歪んだ感じで歌ったりする。
これがやっぱ「歌手」それぞれの「歌い方」であって、
これを構築することによって「その人らしい」という「個性」にまで昇華するわけだ。
昔、嫁が花嫁道具として持って来た「関西ブルースCD」とか何とかいうコンピレーションアルバム。
中に入ってた優歌団の木村さんが歌うポップス調の曲・・・
いや〜・・・恐れ入った・・・
ひとつとして正しい音程がない(笑)
それでいてひとつとしてイヤな音程でない。
歌手の上手い下手はワシにはようわからんが、
「こいつ下手!!(>_<)」と思う歌手は、その音程に対して「責任」を持ってない。
こんな歌手は「嫌い」だなといつも感じる・・・
ドラムのリズムとは「戦いの連続」という話を書いたことがあるが、
歌とはもっと高度な戦いの連続なのだ。
木村さんはその戦いを「天使のダミ声」という「飛び道具」を使って命がけで戦ってらっしゃる。
Auto-Tune的に全然正しくないこの音程の全てに木村さんの「ドラマ」があり、
それは強いて言えば木村さんの「人生」である。
だから木村さんの歌を聞いて涙が出るのである。
「木村さん・・・あんたはやっぱ凄いわ」と泣くのである。
もともと「喉」という楽器はピアノなんかと違って、
「ド」の鍵盤を押したら必ず正しい「ド」の音程が出るものではない。
どのぐらいの喉の絞め方をしたらだいたいどのぐらいの音程かを経験則で習得しているだけの話なのだ。
だからいざ歌い出したらその歌い始めの音程がちょっとずれてるなんて当然のことで、
それをコンマ何秒の間に命がけで修正する。
これをあからさまにやると「音程を探ってる」となってブーイングを食らう。
そんなレベルではない。
木村さんのような飛び道具でなくても、
歌手はみんなご自身の武器を持っていて、
それを縦横無尽に使いながら命がけで音程をどこかに帰着させる。
本当に機械のような経験則で何の苦労もなく正しい音程が出せる喉があったとしても、それで歌を歌って人を感動させるとは限らない。
いろんな声色を使い分けれて、何オクターブの声域を持ってたとしても、
それで歌を歌って人を感動させるとは限らない。
まあドラムで言うと、どれだけ手足が早く動いて、
どれだけフレーズをたくさん持ってて何でも叩けたとしても、
それで人を感動させるプレイが出来るかというのは全然違う問題なのである。
武器が少なくたって、それを使って命がけで戦ってる人の方が人を感動させられたりするから音楽は面白い。
英樹さんの場合、まあ武器はたくさんあるのだろうが、
ワシはあの語尾でちょっと力を抜いて50も過ぎて甘えた感じでシメる落とし方に胸キュン(死語)となる。
人に歴史あり!!その歴史が形になるのが音楽なのである。
ドラマーの諸君、毎日メトロノームで練習してても上手くならんよ。
世の中に出て泣いたり笑ったりいろんなことを経験して、
それを自分なりに戦って乗り越えて来て初めて、音楽の中での戦いがわかる。
歌の話ばっかになったのでドラムの例でシメさせて頂こうと思う。
中国に許魏というシンガーソングライターがいて、
彼の復帰作である「時光・慢歩(ShiGuan ManBu)」というアルバムのドラムを叩かせて頂いた。
このアルバムが中国ロックの金字塔を打ち立てて、
それを叩いているドラマーであるということからファンキー末吉の名は中国でまた伝説化した。
何も有名アルバムに参加したからということではない。
ワシは許魏の「歌」をドラムで「歌った」のである。
彼が西安から出て来てレコード会社と契約して、
一番貧乏だった頃、彼の部屋でそのデビューアルバムのデモを聞かせてもらった。
中国ロックに新しい時代が来たと感じた。
その後デビュー、そこそこヒットはするがしょせんはロック、
大金を稼ぐことも出来ず、彼は傷心して田舎に帰ってゆく。
一説によるとそこから麻薬に手を出して、
禁断症状から抜け出すためにドアや窓を全部打ち付けて、
自分を椅子に縛り付けて耐えた(そんなことが出来るのか?)
それを救いに行ったのがこのアルバムのプロデューサーの栾树(Luan Shu)で、
そのドアを開けて彼を縛っている縄を解いて、
そしてその時に「こんな曲が出来たんだ」と言って歌って聞かせたのが「蓝莲花(蓮の花の意)」という曲であるという都市伝説。
聞き終わった栾树は彼を抱きしめてこう言った。
「お前はもう大丈夫だ。一緒に北京に帰ろう」
そしてこの復帰アルバムを作ることとなり、
許魏が指名したドラマーがワシだったというわけだ。
今ではもう彼のバックはやっていないが、
ある日イベントで許魏が出演していて他のドラマーが叩いてるこの曲を聞いた。
ワシはそのドラマーを呼び出して説教した。
「お前は何も分かっていない!!」
「没有什么能够阻挡(何もこれを阻止出来るものはない)」という歌い出しで始まるこの曲・・・
その歌に続いてドラムが入るのだが、そのシンバルが彼は少し強かった。
「アホか!!あんなんじゃ許魏のメッセージをぶち壊しだろ!!」
強く叩けばこのメッセージは「おりゃー!!誰にも邪魔させんぞー!!」というメッセージとなり、
弱く叩けば「もう無理なんです。誰にも邪魔させないなんて・・・」みたいな意味になる。
許魏のメッセージというのは「絶望の中に一筋の光を見た」というものだとワシは思ってる。
北京での初ライブを終えた時の打ち上げで本人にこのことを言ったら、
「それ以上言わないでくれ、泣いちゃう・・・」
と笑った。
ちょうどいいある強さのシンバルだけが唯一「絶望の中の一筋の光」を表現出来るのだ。
その強さで叩いてこそ客は号泣するのだ。
その歌い手の人生に・・・
リズムとは「初恋」のようなものとよくワシは言う。
「オッサンが何をまあロマンチックな」と笑われることもある。
弱く叩けば失ってしまう、強く叩けば壊してしまう、
そんな一発を命がけで叩くことこそが「歌う」ということなのだ。
音程なんてどうでもいい、外れているのもわからないような人にはこの戦いはわかるまい・・・
英樹さん素敵な歌をどうもありがとう。
オマケ:2万人が泣いた許魏伝説の北京ライブ
中国に行けば今だに初対面の人に「このコンサート行きました」とか「DVDで見ました」とか言われることが多い。